二十四節気による季節を表す言葉に「穀雨」というものがあります。
今回は、穀雨はいつなのかという疑問に答えながら、この穀雨の由来は何なのか、具体的な意味やその時期の食べ物は何なのか、2024年はいつなのかなど、今でも日本で残っている風習はあるのかを調べてまいります。
穀雨という言葉だけではわかりにくくても他の二十四節気や雑節と交えるとわかりやすくなります。
- 穀雨の意味や由来は?
- 2024年の穀雨はいつ?
- 穀雨の時期はどんな季節なの?
- 穀雨の時期の旬な食べ物は?
- 穀雨の時期の風習は?
- 穀雨の季節の花は?
- 穀雨に関するよくある質問まとめ
- 「穀雨」とは、具体的にはどのような時期を指すのですか?
- 「穀雨」の由来や意味にはどのような背景があるのですか?
- この「穀雨」の時期に特有の行事や風物詩はありますか?
- 「穀雨」の時期の気象や気候の特徴はどのようなものですか?
- この節気「穀雨」には、体調管理や健康の観点から注意することはありますか?
- 二十四節気の中で「穀雨」は何番目に位置するのでしょうか?
- 「穀雨」は、どのような食材が旬として注目される時期ですか?
- 「穀雨」の期間中に行われる伝統的な風習や行事は、他にもあるのでしょうか?
- 「穀雨」の時期に特有の風邪や病気、アレルギーについて注意すべきことは?
- この「穀雨」の時期に合わせておすすめの過ごし方や活動はありますか?
- まとめ
- 穀雨以外の二十四節気一覧を紹介!
穀雨の意味や由来は?
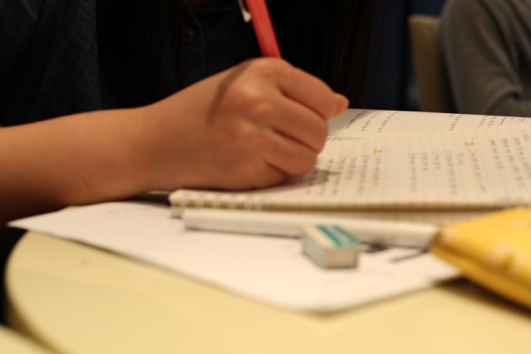
二十四節気の1つである穀雨というのは名前からなんとなく察することができるでしょうが、「穀物を育てるのに必要な春の雨を降らせる季節であり、秋の方策を祈る季節」となっています。
中国では梅雨はありませんが、この穀雨のタイミングで雨の量が増えるようです。
ちなみに、この時期の雨は大変貴重なものであり、雨が降らないと不作になるとすら言われているので、この時期の雨には様々な表現が存在しています。
いくつか抜粋して記載すると瑞雨や催花雨や春霖や菜種梅雨といった春の雨を表す表現があります。
瑞雨は穀雨と同じ意味で穀物の生長を助ける雨であり慈雨とも呼ばれます。
催花雨とは植物の開花を促すような雨で、春霖と菜種梅雨は3月や4月に降る長雨という意味になります。
これらはかなり難しい表現なので、今は使っている人も少ないでしょうが、覚えておくと知識人として見られるでしょう。
また、穀雨のイメージが日本とマッチしないと感じている人は、今から2500年前の中国春秋戦国時代の洛陽を中心とした中原で広まった季節の考え方だから、地域による違いがあるとお考え下さい。
洛陽の平均気温を比較すると4月ごろにかけて急激な温度上昇があり5月に入るタイミングではすでに平均気温で25℃を超えているのです。
このように春の訪れが日本よりもはるかに早く、梅雨も台風もないのでそれだけ日本と季節感のずれが発生するようになっています。
2024年の穀雨はいつ?
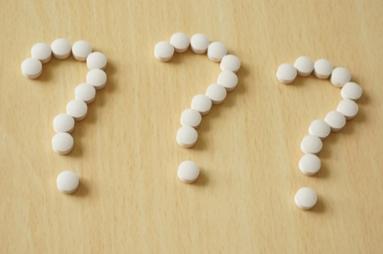
2024年の穀雨は国立天文台発表の報告によると4月19日から5月4日までです。
立春から始まる節気は立春→雨水→啓蟄→春分→清明→穀雨と続いているので、6番目に該当するのです。
ちなみに、7番目が立夏であり、中国における夏のスタート地点と考えられているのですが、日本とは季節感がかなり違いますので夏とか春という考え方をそのままトレースするとズレが発生してしまいます。
また、ちょっとした豆知識ですが、西洋占星術ではこの穀雨が始まるタイミングをおうし座の始まりと考えているので、星座もついでに覚えることができます。
穀雨の時期はどんな季節なの?

穀雨の時期は、日本人にとってはゴールデンウィークに突入する大切な季節という感覚が強いでしょう。
大型連休が訪れるタイミングがこの穀雨になっていると覚えることができれば簡単なので、関連付けて覚えるようにしてください。
二十四節気をより細かく分けた七十二候と呼ばれるものがあり、今まで紹介した二十四節気を初候・次候・末候の3つに分けるのです。
穀雨の七十二候は
初候が葭始生ず
次候が霜止んで苗出ず
末候が牡丹華さく
となっております。
この七十二候は日本における考え方なので、日本における穀雨とは葦が芽吹いて霜が降りなくなって苗が育ち、牡丹が花咲く季節という表現が当てはまるのでしょう。
はっきり言ってゴールでウィークと絡めないと特徴が出てこない季節なので、記載しにくい季節でもあります。
穀雨の時期の旬な食べ物は?

穀雨の時期の旬の食べ物は4月から5月にかけて旬の食べ物となるでしょう。
4月と5月が旬な野菜やキノコ類や豆類はかなりたくさんあり、あしたば・アスパラガス・うど・かぶ・きくらげ・キャベツ・グリーピース・クレソン・こごみ・ごぼう・さやえんどう・さんしょう・しいたけ・ぜんまい・そらまめ・たけのこ・タラの芽・長芋・にら・のびる・ふき・ルッコラ・レタスなどが該当します。
果物はあまなつ・イチゴ・キウイ・グレープフルーツ・夏みかん・マンゴーなどが該当します。
魚だとさわら・しらす・めばるが該当し、海産物ではコウイカ・毛ガニ・とりがい・ホタルイカ・真蛸・もずく・わかめが該当するでしょう。
このように該当するものをいくつか抜粋してみましたが、かなりの量となっていますので、堪能する場合は非常に時間がかかります。
ただし、食べ過ぎると高確率で太ってしまいますので、自分の体重にも気を付けながら食べるようにしましょう。
穀雨の時期の風習は?
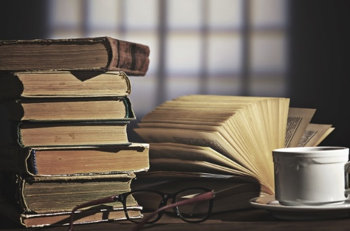
穀雨の時期における風習の中でも知名度が高いのは雑節の1つである八十八夜でしょう。
この八十八夜というのは立春から数えて八十八夜なので、だいたい5月2日や5月3日が該当するのです。
この八十八夜に合わせて摘まれたお茶は非常においしく長生きするという考え方が残っており、静岡や京都といったお茶で有名な場所は新茶のサービスといった特殊なイベントが開催されているのです。
昔から「夏も近づく八十八夜」という言葉で使われていましたが、この穀雨が終わると立春の季節に入りますので、まさにこの歌の通りとなっております。
ただし、この八十八夜という考えは二十四節気だけではどうしても発生してしまう季節のズレを修正し移り変わりを正しく認識させるために特別用意されたもので、これは日本独自のものとなっております。
他にこの雑節は節分・彼岸・社日・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日・二百二十日といったものがあり、いくつかは非常に有名なものとなっています。
穀雨の季節の花は?

穀雨の季節は4月の下旬から5月の上旬なので、その時期に見どころになる花や誕生花として設定されているのが季節の花となるでしょう。
有名どころではスイートピーやチューリップ、ハナミズキやマリーゴールドやフジ、ポピーやライラックなどが該当します。
それ以外にも、誕生花で考えるとカリフォルニアポピー・ルピナス・ムルチコーレ・ホシクジャク・牡丹・シャガ・モッコウバラ・ミヤコワスレ・カルミヤ・ローズマリー・ミヤコグサ・ムラサキハナナ・マーガレット・シバザクラ・フロックスなどが該当するでしょう。
七十二候の解説でもあったように牡丹が誕生花として登場していますので、この中でもひときわ目立っております。
日本ではそこまで重宝されていない牡丹ですが、中国では花の王様といった扱いを受けるほどかなり愛されている花なので、まさにぴったりと言えるのではないでしょうか。
穀雨に関するよくある質問まとめ
「穀雨」とは、具体的にはどのような時期を指すのですか?
「穀雨」は二十四節気の一つで、毎年4月20日前後に訪れる時期を指します。
この名前は、春の雨が穀物の成長を助けることから名付けられました。
この時期は、種まきが終わり、農作物の発芽や成長が盛んになる季節を示しています。
「穀雨」の由来や意味にはどのような背景があるのですか?
「穀雨」の名前の由来は、春の終わりの雨が稲や麦などの穀物の育成を助けることからきています。
中国の古代の農業社会では、この時期の雨が穀物の育成にとって非常に重要であったため、特にこの名前が付けられました。
この「穀雨」の時期に特有の行事や風物詩はありますか?
「穀雨」の時期には、日本では「餅まき」の行事が行われる地域もあります。
これは、新しい季節の豊かな収穫を願って行われるものです。
また、風物詩としては、春の最後の桜の花が散りゆく情景や、新緑が目を楽しませてくれることが挙げられます。
「穀雨」の時期の気象や気候の特徴はどのようなものですか?
「穀雨」の時期は、春が終わり夏へと移行する過渡期となります。
徐々に気温が上昇し、多くの地域で穏やかな気候となりますが、一方で春の最後の寒さや急な雨が降ることもあります。
この時期の雨は、農作物の成長を助ける重要な役割を果たします。
この節気「穀雨」には、体調管理や健康の観点から注意することはありますか?
「穀雨」の時期は、気温の変動が激しくなることがあるため、風邪や体調不良を引き起こしやすい時期とも言われています。
特に、急な気温の下降や湿度の変化による体調の変動に注意が必要です。
また、新緑の季節となるため、花粉症の症状が出る人も増えることが予想されます。
二十四節気の中で「穀雨」は何番目に位置するのでしょうか?
二十四節気の中で「穀雨」は6番目の節気として位置しています。
春の最後の節気として、次の節気「立夏」で夏の始まりを迎えることになります。
「穀雨」は、どのような食材が旬として注目される時期ですか?
「穀雨」の時期には、新緑の季節となり、たけのこやわらびなどの山菜が特に旬となります。
また、春キャベツや新玉ねぎなどの春野菜も豊富に市場に出回る時期となります。
「穀雨」の期間中に行われる伝統的な風習や行事は、他にもあるのでしょうか?
「穀雨」の時期には、一部の地域で種まきや田植えの準備をする「田打ち」の風習があります。
これは、次の豊作を願い、農作業の安全を祈念するための行事です。
「穀雨」の時期に特有の風邪や病気、アレルギーについて注意すべきことは?
「穀雨」の時期は、温暖な日が続くことで花粉の飛散量が増加する場合があります。
そのため、スギやヒノキの花粉症の人は特に注意が必要です。
また、気温の変動や湿度の変化による風邪を引きやすい時期でもありますので、体調管理に気を付けることが大切です。
この「穀雨」の時期に合わせておすすめの過ごし方や活動はありますか?
「穀雨」の時期は、自然が生き生きとしてくる時期です。
散歩やハイキングを楽しむのに最適な季節となります。
特に、新緑や春の花々を楽しむことができる公園や山間部への訪問はおすすめです。
また、春の味覚を楽しむための食事や料理にも挑戦してみると、この時期ならではの楽しみ方ができるでしょう。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は穀雨について詳しく解説いたしました。
日本では八十八夜といった特殊な風習がしっかりとのこっていますので、何らかのイベントを楽しみたいという方はお茶の名産地に訪れるといいでしょう。
穀雨以外の二十四節気一覧を紹介!

ここまで二十四節気の穀雨について詳しく解説してきましたが、他にも23個も存在していることはご存知でしたか?
それぞれにいろんな意味や由来があり、見てみると面白い内容になっています。
これを機に穀雨以外の二十四節気についても学んでみましょう!



コメント