日本にある様々な祝日の中の一つが春分の日です。
しかし、この春分の日とはどのような意味があるのか、2024年はいつなのか、具体的な決め方はどうなっているのか、なぜその日は休みになっているのかなど、より深く疑問を突きつけられると答えられる人は激減してしまうでしょう。
今回はこの春分の日とはいったい何なのかを詳しく解説いたします。
2024年の春分はいつ?
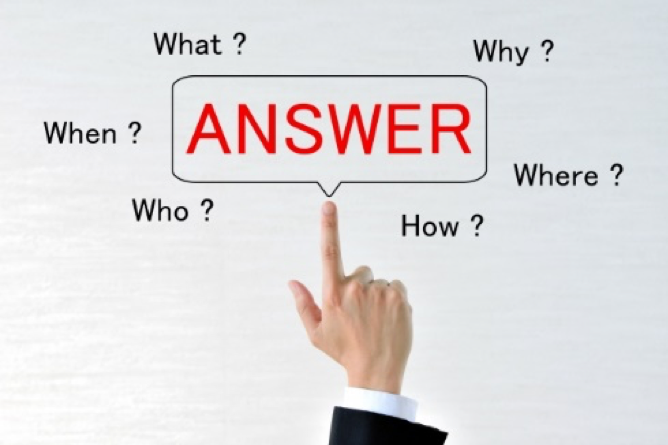
春分は2024年だと3月20日からとなっております。
これが「春分の日」となると春分に切り替わった日なので2024年なら3月20日となっています。
春分の日の意味や由来!

春分の日は、黄道を360度に分割した黄経の起点が春分点でありその日が春分の日となります。
地球の赤道をそのまま延長した線を「天の赤道」というのですが、この「天の赤道」と太陽の通り道が交差した部分が黄径ゼロ度であり春分の日なのです。
この黄径ゼロ度に到達した日は太陽が真東から昇って真西に沈みとなりますので、昼と夜の長さが同じ日となります。
昼と夜の長さが同じになるのは黄径ゼロ度の春分の日と黄径180度の秋分の日の2回しかありません。
もともと「春分」は春の中間の日を意味する言葉であり、二十四節気の春を表す節気においても「立春⇒雨水⇒啓蟄⇒春分⇒清明⇒穀雨」と4番目に来ています(啓蟄の終わる瞬間、つまり春分が始まる瞬間が真ん中となる)。
二十四節気は太陽の動きに基づいて考えられており、その根幹にあるのが「春分・夏至・秋分・冬至」という「二至二分」なのです。
春分の日の決め方は?

今まで記載したように、春分の日とは太陽が起点となる春分点を通過した日となりますので、太陽と地球の位置関係によって決められるのです。
ただし、1年は365日としていますが正確には約365.24219日と端数が発生しているので、この端数によるずれを修正するためにうるう年が存在しているのです。
このうるう年の考え方によって1日分ずれの修正が4年に1回行われるので、春分の日が3月20日になったり21日になったりします。
太陽と地球の位置関係を確認して計算するには正確な測定する装置及び機関が必要なので、日本ではその役割を国立天文台が担っており、国立天文台から正式発表として春分の日はいつになるのかといった報告が毎年されるようになっているのです。
偉い人が勝手に決めているのではなく、きちんとしたルールが存在しているのです。
肉眼ではこの太陽の位置や角度を確認するのはほとんど不可能なので、国立天文台の発表を毎年確認して、そこの情報を活用するというスタイルのほうがいいでしょう。
春分の日はなぜ年によって変わるの?

秋分の日や春分の日がずれてしまう最大の理由が1年は365日ですが、地球が太陽のまわりを回る日数、いわゆる公転に必要な日数はぴったりと365日ではないのが理由です。
こちらも先ほど記載したように、この公転にかかる日数は約365.24219日なのでこの端数分だけ二十四節気が始まるタイミングもずれていきます。
このずれを修正するために1年が366日となるうるう年があるのですが、うるう年があると1日増えるのでその結果秋分の日や春分の日といった区切りも前の日とずれていくのです。
春分の日はこのようなズレの修正によって3月20日と21日の間をいったり来たりしています。
稀に3月19日や3月22日になることもあるようですが、3月19日が春分の日になるのは2092年とはるか先といわれており、3月22日になるのは今から約100年前の1923年とめったにない現象となっています。
春分の日にはなぜお墓参りや先祖供養をするの?

春分の日のちょっとした行事としてお墓参りや先祖供養を行ったことがあるという人も多いでしょう。
もともと日本では古来から太陽信仰が盛んであり、真東から太陽が昇って真西に沈む春分の日は特別の日という考え方が根付いていました。
そこに仏教が伝来して広まり、その教えである「極楽浄土は西に存在する」という彼岸の考え方が受け入れられることで、太陽が真西に沈む春分の日は先祖供養の日という考え方が誕生したのです。
この考え方が日本全国に広まっているので、春分の日はお墓参りに行くとか先祖供養を行うという風習が今でも残っています。
春分の日はなぜ国民の祝日で休みなの?

戦前は春分の日は天皇家の先祖代々の御霊を供養する「春季皇霊祭」を行う祭日として扱われていました。
戦後の1947年にはこのような祭日はなくなってしまいますが、春分の日という祝日として今でも残っているので、祝日で休みになっているのです。
戦前は春分の日はあくまでも天皇家の御霊に対する祭事という扱いだったのですが、今では春分の日は個人的な供養を行う日であり自然をいつくしむ日という扱いになっています。
1908年9月19日制定された「皇室祭祀令」は「春季皇霊祭」や「神武天皇祭」、「秋季皇霊祭」など様々な大祭認定を行っていましたが、それらの大祭認定は1947年にこの「皇室祭祀令」が廃止されることによってなくなっています。
春分の日に食べる代表的な「食べ物」は?

春分の日はお彼岸に該当するので、そのお彼岸にちなんだ食べ物が代表的な食べ物となるでしょう。
具体的にはお彼岸向けといわれているのが精進料理でしょう。
野菜・穀類・豆類・海藻・果実を中心にした料理を食べることになります。
精進料理の基本は肉類や魚介類といった動物性の食材を一切食べないことなのですが、現代日本ではここまで厳密に春分の日のしきたりを守っている人も少ないでしょう。
また、古来より魔よけ効果があるといわれていた小豆を使ったものが好まれていたので、牡丹餅やおはぎを食べる風習もあります。
春分以外の二十四節気は何があるの?

ここまで春分の意味や由来などについて詳しく紹介してきましたが、二十四節気は春分以外にもまだまだあります。
残り23個ありますので、ぜひチェックして二十四節気について知識を深めてみてください。
下記にまとめましたのでチェックしてみましょう。
立春
雨水
啓蟄
清明
穀雨
立夏
小満
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
処暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
春分に関するよくある質問まとめ
「春分」とは、具体的にどのような日を指すのでしょうか?
「春分」とは、春の中間を示す日を指し、この日には昼と夜の長さがほぼ同じになることからその名がついています。
太陽が天の赤道を通過する日であり、春の訪れを象徴する節気として古くから注目されてきました。
日本における「春分の日」の意義や由来は何でしょうか?
日本では、「春分の日」は国民の祝日として定められており、自然をたたえ、生物を尊重する心を養う日とされています。
古代からの先祖崇拝の日でもあり、多くの家庭ではお墓参りをする習慣があります。
「春分」の時期におすすめの行事や過ごし方はありますか?
「春分」の時期には、春の訪れを感じられる行事や過ごし方が多くあります。
桜の花見や新緑を楽しむピクニック、また、新たなスタートを切るこの時期に合わせて大掃除を行う家庭も多いです。
また、春の新鮮な食材を楽しむ料理や、春の装いを取り入れたファッションもおすすめです。
他の国々での「春分」の習慣や祝日はどのようなものがあるのでしょうか?
多くの国々でも「春分」は春の訪れを示す特別な日とされています。
西洋では、「春分」はオスタラとして知られ、新しい命の誕生や再生を祝う日としています。
特にヨーロッパの一部の地域では、卵やウサギを象徴とするお祭りや行事が行われることがあります。
「春分」の日には、どのような食材や料理が季節感を感じられるのでしょうか?
「春分」の時期には、春野菜が旬を迎えます。
たけのこや菜の花、うどや新玉ねぎなど、春らしい食材を使用した料理が多く楽しまれます。
また、この時期の魚介類も豊富で、サバやイワシなどが新鮮に入手できるので、これらの食材を取り入れた料理で春の訪れを味わうことがでしょう。
「春分」の日と「春分の日」の違いは何ですか?
「春分」は、二十四節気の一つとして太陽が天の赤道を通過する日を指します。
一方、「春分の日」は、日本の国民の祝日として、春分を近くの日曜日に設定されることが多いです。
この日は、自然と生物を尊ぶ心を育む目的で定められています。
「春分」の前後の節気は何ですか?
「春分」の前の節気は「啓蟄」、後の節気は「清明」です。
これらの節気も春の中期を示すもので、自然の変化や気候の変動を感じ取ることができる時期です。
春分が近づくと、どのような変化が自然界で観察されますか?
春分の時期になると、日が長くなり、気温も徐々に上昇します。
これに伴い、動植物の活動が活発になり、桜の花が咲き始める地域も増えてきます。
また、多くの鳥たちが渡りを始め、春の訪れを告げるさえずりが聞こえるようになります。
「春分」の日に特定の風味や香りを楽しむ習慣はありますか?
「春分」の日に特定の風味や香りを楽しむ習慣は、地域や家庭によって異なりますが、春の新鮮な食材を取り入れた料理を楽しむことが多いです。
たとえば、若筍や春キャベツなどの旬の野菜を使用した料理や、春の花々の香りを楽しむこともおすすめです。
「春分」に関連した伝説や物語はありますか?
春分に関連した伝説や物語は、古代の神話や伝承に見られます。
例えば、日本には春分の日を迎えると、生と死の境界が曖昧になるという伝承があり、先祖の霊がこの世に戻ってくると信じられていました。
また、欧米の伝説では、春分の日は再生や新しい始まりを象徴する日とされ、多くの物語や伝説に登場します。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は春分の日とは何なのかを記載しました。
国民の祝日に該当する春分の日が昼と夜の長さが同じ日であるということは知っている人も多いでしょう。
しかし、なぜ休みだったのか、なぜ春分の日が20日だったり21日だったりするのかまでしっかりと答えられる人は少ないです。
仲間同士のちょっとした話題提供にもこの知識は確実に役立ちますので、忘れないようにしてください。



コメント