立春や立夏は効いたことがある人でも「雨水」まで聞いたことがあるという人は少ないでしょう。
今回はこの雨水とはどのような意味や由来があるのか、2024年はいつなのか、雛人形を飾ると効果的というお話の信憑性はどうなのか、このタイミングで食べる食べ物は何かあるのかを具体的に解説いたします。
まずはこの雨水の読み方から始めることになるでしょう。
後半では雨水以外の二十四節気についても触れているので、ぜひご覧ください。
雨水の意味や由来!

雨水の由来は中国の春秋戦国時代に作られたといわれている二十四節気にあります。
その中には立春や秋分や夏至と言った有名なものがあり、現代日本でも通じるものが多数存在しているのです。
また、日本の場合は独自に発展した陰陽道にも密接なかかわりがあるのでいくつかの風習や文化においてその名残を確認することができます(節分やお正月の文化がまさにそれ)。
この雨水は「暦便覧」によれば「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」という記述があり、意味は「雪が雨に変わって氷が溶けて水になるような暖かい季節になる」と考えられるでしょう。
ただし、この考え方は中国ものであり日本のそれとはずれることも非常に多いです。
「二月の下旬でも雪は降るしものすごく寒いし春だとは思えない」という考え方も至極当然ですが、中国では畑に肥料を入れるタイミングとして捉えていたぐらいなので国による季節の違いとして考えるしかないでしょう。
2024年の雨水はいつ?正しい読み方は?

雨水は1年を24分割した戦国時代の中国で始まった二十四節気の第2に該当する季節で、2024年は2月19日です。
ちなみに読み方は「うすい」なので、「あまみず」と呼ばないようにしましょう。
ちなみに2028年までならとある計算式が成り立ちます。
それは西暦を4で割るというシンプルなもので、あまりが1だった場合は2月18日が雨水となり、それ以外は2月19日が雨水になるというものです。
シンプルな方法ではありますが、時候の挨拶として「立春の候」といった言葉を使おうと考えている方は雨水のタイミングを理解してそのタイミングから逸しないようにしましょう。
雨水の時期に雛人形の準備をするといいって本当?

雨水の時期とは2月19日ぐらいと記載しましたが、正式にはそこから約15日間は雨水となるのです。
つまり、2月19日スタートの場合は3月4日も雨水に該当します。
つまり、この雨水の時期は、ひな人形を飾る3月3日の桃の節句も当てはまるのです。
このひな人形はもともと「雨水の時期に飾ることで良縁に恵まれるようになる」という考え方から始まっているものなので、2月の下旬から飾るのは正解なのです。
本格的な良縁を狙っているという方は雨水が始まったタイミングからひな人形を飾っておくのもいいでしょう。
ただし、ひな人形は桃の節句である3月3日を過ぎたらすぐに片付ける必要があるといわれていますので、ぎりぎりに飾るのは辞めましょう。
ものすごくあわただしくなってしまいます。
雨水の時期に旬な食べ物は?

雨水のタイミングで「これを食べなければいけない」というものはありませんが、旬の食べ物はいろいろとありますのでそちらは意識したほうがいいでしょう。
具体的には春キャベツ・フキノトウ・素魚・ハマグリ・タラの芽・ふぐ・八朔・カキ・デコポン・アサリなどが該当します。
個人的に非常においしいと感じるのが山菜の類で、タラの芽のてんぷらとかは最高においしいと感じております。
おいしい春キャベツを使ったお料理もがっつりと食べられると幸せな気分になるでしょう。
季節とは関係ありませんが、この春キャベツととんかつがセットになるだけでお食事も楽しめます。
ただし、この季節というのはまだまだ寒く運動量が大きく低下する時期でもありますので、旬の食べ物を大量に食べてしまうと高確率で太ります。
自分の運動量も考えたうえでお食事の量もちゃんと調整するようにしましょう。
旬の食べ物はついつい食べ過ぎてしまうので、寒い時期は要注意です。
雨水の季節感は?春一番や三寒四温もこの時期なの?

雨水と言われてもいまいちイメージがわかないという人もいるでしょう。
もともと、この雨水というのは「雪が雨に変わって寒さが抑えられて、草木が芽吹くタイミング」となっておりますので、実は春一番のタイミングもこの雨水の時期となります。
ただし、いきなりの大雪といった天候の崩れが発生するタイミングでもありますので、四字熟語である三寒四温の時期でもあるのです。
もともとは中国北東部を意味する言葉であるのですが、この三寒四温を何度も繰り返しながら最終的には温かくなっていきます。
雨水の時期の行事やイベントは何があるの?

何のイベントもない雨水の時期に見えてしまいますが、日本ではひな祭りの時期と被っているので大きなイベントと言えばこのひな祭りとなるでしょう。
それ以外には長崎県にある愛宕神社の相浦愛宕まつりや、大阪の大阪天満宮のてんま天神梅まつりといったイベントもありますので住んでいる地方限定ではありますが楽しめるタイミングでもあるのです。
二十四節気発祥の地である中国ではこの雨水の時期になると、「元宵節」が行われるようで、海外でもイベントが楽しめるようになっています。
2月下旬のイベントといわれてもあんまりイメージがわからない人も多いと思います。
上旬ならばさっぽろ雪まつりとか、節分とか、針供養とか、ちょっと遅れてバレンタインデーもあるのですぐに浮かぶのですがどうしても隙間の時期というイメージが強くなっています。
雨水の季節の花は何?

雨水の花とはいわゆる二月下旬で有名な花が該当するでしょう。
有名な花だとカンツバキ・アネモネ・山茶花・クロッカス・シロツメクサ・シクラメン・ナズナ・チューリップ・ヒイラギ・ローズマリーあたりが該当します。
誕生花に限定すると2月は梅が該当します。
2月19日の誕生花はたんぽぽ、20日はカルミア、21日はネモフィラ、22日はローダンセ、23日はコブシ、24日はサクラソウ、25日はカランコエ、26日はフクジュソウ、27日はマドンナリリー、28日はヘリクリサム、3月1日は杏子、2日はストック、3日はレンゲソウ、4日はアイスランドポピーとなっているようです。
雨水に関するよくある質問まとめ
「雨水」とは具体的にどのような時期を指すのでしょうか?
「雨水」は二十四節気のひとつで、冬の終わりから春の初めにかけての期間を指します。
この時期は、雪が解けて雨が増えることから「雨水」と名付けられました。
大体2月19日から3月5日頃までの日を指します。
「雨水」の期間中に特有の気象変動や自然の動きはあるのでしょうか?
「雨水」の時期は、徐々に温かくなり始め、雪が雨に変わり始めることが多いです。
また、植物や動物たちも春を迎える準備を始めるため、芽吹きの初めや動物の活動が増える兆しを見ることができます。
「雨水」に関連する言い伝えや風習は存在しますか?
「雨水」に関連する言い伝えとしては、「雨水の日に雨が降らないと豊作」というものがあります。
また、この時期には種まきを始める地域も多く、新しい生命の始まりを感じることができる期間とされています。
「雨水」の節気はどのような料理や食材が旬となるのでしょうか?
「雨水」の時期は、春の訪れを感じることができる食材が多く登場します。
特に筍やうど、春菊などの春の山菜が出始め、また魚介類ではカレイやヒラメなどが旬を迎えることが多いです。
「雨水」の後、次に訪れる節気は何でしょうか?
「雨水」の後に訪れる節気は「啓蟄」です。
「啓蟄」は春が深まる頃を指し、地中に隠れていた虫たちが活動を始めることを意味します。
この時期は、より一層春の気配を感じることができます。
「雨水」の名前の由来は何ですか?
「雨水」の名前は、この時期に冬の寒さが和らぎ、雪ではなく雨が降ることが増えることから来ています。
文字通り、雪から雨へと変わる過渡的な時期を示す節気として、古くから日本の暦に記されています。
二十四節気の中で、「雨水」はどの位置に位置していますか?
二十四節気の中で「雨水」は2番目に位置しています。
「立春」の後、「啓蟄」の前に来る節気で、冬から春への移行期を感じることができる重要な時期となります。
「雨水」の時期に適した行事や活動はありますか?
「雨水」の時期は、自然界が春に向けて動き始める時期です。
この時期には、初春の山菜採りや、新しい季節を迎える準備としての大掃除をする家庭も多いです。
また、庭や畑の手入れを始めるにも適した時期とされています。
「雨水」の期間中に身につけるべきファッションやアイテムはありますか?
「雨水」の時期はまだ寒さが残るため、春色を取り入れつつも保温性のあるアイテムを組み合わせるのがおすすめです。
また、雪から雨へと天気が変わることを考慮して、撥水性のあるコートや靴を選ぶのも良いでしょう。
「雨水」の時期に特有の健康上の注意点は何でしょうか?
「雨水」の期間は、気温の変動が激しいことが特徴です。
そのため、風邪やインフルエンザを引きやすい時期ともなります。
暖かくして外出し、体調管理をしっかりとること、そして手洗いやうがいをこまめに行うことが大切です。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は雨水について詳しく紹介いたしました。
雨水は日本でそこまでなじみがある季節ではありませんが、二十四節気を理解する上では避けては通れない季節なので、どのタイミングなのかは理解しておきましょう。
単語と季節が結び付けられれば、自然と頭の中から出てくるようになりますので、旬の食べ物や花からイメージできるようになるとかなり簡単になります。
雨水以外の二十四節気一覧はこちら!

今回は雨水について詳しく解説しましたが二十四節気の字の通り、雨水以外にも23個が存在しているのです。
これを機に雨水以外の二十四節気についても学んでみませんか?
知らなかったことをたくさん学べると思いますよ。
ぜひ参考にしてみてください。
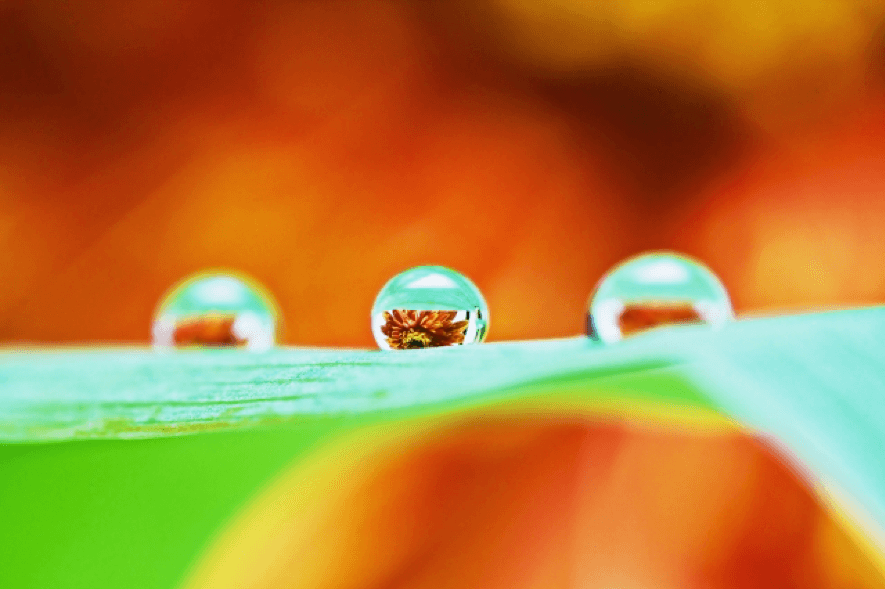


コメント