雑節は、日本の伝統的な暦の一部として、現代においてもその価値が認められ、活用されています。
雑節を理解することで、日本の暦をより深く、楽しむことができるでしょう。
本稿では、雑節の意味と各節の読み方を解説し、それらを一覧形式でのカレンダーや各雑節の由来と共に掲載します。
雑節に興味を持つ方々にとって、その背景や日付を一覧で確認できることは、大いに参考になるはずです。
雑節に関する知識を深め、日本の暦の豊かさを改めて感じてみてください。
雑節の意味や由来と正しい読み方は?

雑節(ざっせつ)は、日本の伝統的な暦において、二十四節気や五節句以外に設定された特別な日々で、季節の移り変わりをより分かりやすく捉えるために存在します。
これらの日々は、具体的には節分(せつぶん)、彼岸(ひがん)、社日(しゃにち)、八十八夜(はちじゅうはちや)、入梅(にゅうばい)、半夏生(はんげしょう)、土用(どよう)、二百十日(にひゃくとおか)、二百二十日(にひゃくはつか)という9つの節目を指します。
これらの中には、現代でも広く知られ、継承されているものがある一方で、ほとんど耳にすることのない、知らなかったという節目も含まれています。
二十四節気や五節句だけでは表現しきれない季節の節目を、雑節が簡潔にまとめ上げているのです。
これらは、昔の人々にとって非常に役立つ目安だったことでしょう。
それぞれの雑節は日々の生活や農作業を反映したものであり、その背後には日本の文化や風習が深く根ざしています。
雑節の簡単な覚え方!
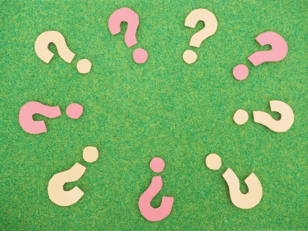
節分や彼岸は多くの人が知っている雑節ですが、社日や半夏生のような、あまり馴染みのない雑節を覚えるには、それらがいつなのかをしっかりと暗記することが重要です。
さらに、それぞれの雑節がどんな日なのかを簡潔に理解し、容易に連想できるようにすることもポイントです。
例えば、社日はその土地の守護神である産土神を祀る日であり、豊作祈願と収穫に感謝する日です。
これは春と秋の年に2回行われます。
また、半夏生は「この日までに畑仕事を終えるべき目安日」とされています。
これらのように、あまり馴染みがない雑節の意味や由来を調べ、それがいつ行われるのかもしっかりと記憶することで雑節を理解しやすくなるでしょう。
雑節一覧カレンダー
それでは先に紹介した9つの雑節は一体いつなのか、どのような意味や由来があるのかを簡単にまとめていきましょう。
マイナーな物でも中身が理解できれば覚えやすくなりますので、文字だけ丸暗記するのでは無く何が行われる日なのかを理解することから始めてください。
そうすれば連想ゲームのように思い出すことができます。
節分【せつぶん】

節分とは今では「鬼は外、福は内」と良いながら豆まきをする日です。
なんとなくその行動から予想はできるでしょうが、「邪気を祓う日」となっております。
ただし、この節分とは二十四節気における季節の節目を示しており本来の意味なら立春・立夏・立秋・立冬の前日にあります。
ただし、年をまたぐ立春の前の節分が一番邪気が溜まると言われており、他の3つの節分よりは豪華な祭事が行われ、今では立春の前の日が節分となりました。
ちなみに、この豆まきは中国の鬼を追い払う行事である追儺が変化して一般大衆にも行いやすくなったものであり、元の追儺とはやり方も大きく異なっています。
彼岸【ひがん】

彼岸とは春分・秋分を中心として前後各3日を合わせた合計7日間の期間をさします。
今の日本ではご先祖様を供養する期間となっていますが、元々は仏教用語における迷いの世界から悟りの世界へ至ることやその過程の修行の事である波羅蜜からきています。
この波羅蜜を別の仏教用語で置き換えると到彼岸というのですが、いつからかこの彼岸が極楽浄土がありご先祖様が住まう場所という認識になって、東に此岸(この世)と西に彼岸(あの世)があるなら春分や秋分のように真東から太陽が出て真西に沈む日は一番彼岸に通じる日という考え方が誕生し、さらにそこから変化して「お彼岸=ご先祖様に供養する日」となったのです。
社日【しゃにち】
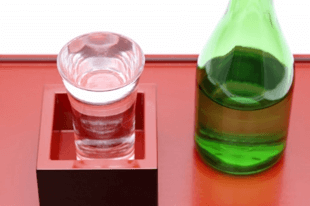
雑節の中でも特別に馴染みが薄い社日は春分または秋分に最も近い戊(つちのえ)の日が社日となります。
要するに3月17~25日と9月18~25日のどれかが社日ということです。
いわゆる生まれた土地の守護神を祀る日で、春の社日にお酒を飲むと耳が良くなるという風習もあります。
このお酒を治聾酒(じろうしゅ)と言うのです。
由来は古代中国では「社」とは土地の守護神という意味があるので、そこから社日になったと言われております。
八十八夜【はちじゅうはちや】

今の日本人でも聞いたことがある八十八夜は立春を1日目としてから88番目の日であり、霜が発生するかどうかを見極める日となっています。
そのため、農家の方々は本格的に畑仕事を行うかどうかを決める基準日となっていますし、お茶の場合は茶摘みを行う時期になるので、お茶にちなんだイベントが日本各地で行われています。
入梅【にゅうばい】
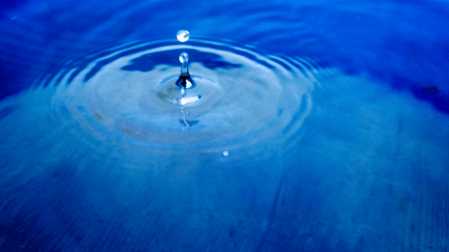
入梅は天気予報が発達していないときに設定された梅雨入りを示す日です。
今では正確な気象予報がありますので、気象庁から梅雨入り宣言がされますが、昔は暦上の梅雨入りがこの入梅だったのです。
半夏生【はんげしょう】

これも現代日本では非常に馴染みが薄い雑節で、球上の黄経100度に達する日がこの半夏生となります。
半夏生は畑仕事や田植えを終わらせる基準日であり、関西では半夏生にタコを食べて豊作祈願をして香川ではおうどんを食べる日にもなっております。
由来は七十二候の1つである「半夏生(はんげしょうず)」からきております。
土用【どよう】

土用の丑の日でも知られている土用とは五行に由来する雑節で、四立と呼ばれる立春・立夏・立秋・立冬の前の約18日間が該当します。
五行思想では万物は火・水・木・金・土の5種類の元素から成り立つという思想があり、春に木気、夏に火気、秋に金気、冬に水気が割り当てられているのです。
そして足りない土用は季節の変わり目に割り当てられているのでこのような割り振りとなっています。
実際に365日を5で割ると73日となりますので、この割り振りが日にち的にもだいたい正しいことがわかります。
また、この土用の期間は土の気が盛んになるので土いじりがNGになるといった特殊なルールが存在します。
二百十日【にひゃくとおか】

二百十日とは立春から数えて設定された日です。
本来の意味は台風に対する警戒を促す日だったのですが、関東大震災が9月1日にあったことからこの台風に対する警戒も合わせて防災の日に認定されて、その日を含んだ1週間が防災週間となっています。
本来ならば台風被害を警告する日だったのですが、今ではあらゆる震災を警告する日になったのです。
二百二十日【にひゃくはつか】

二百二十日も二百十日と一緒で台風に対する被害を警告する日であり、立春から数えて220に目のこととなっています。
意味は二百十日とほとんど同じであり、農家にとっての厄日となっているようです。
雑節に関するよくある質問まとめ
日本の伝統的な雑節とは具体的にどのようなものですか?
日本の伝統的な雑節とは、主に農作業や季節の移り変わりに関連した、古来から伝わる節目のことを指します。
例えば、稲作に関連する「田植え節」や、季節の変化を感じる「入梅」などがあります。
これらは具体的な日付で決まっているわけではなく、自然の変化に合わせて祝われることが多いです。
雑節は現代の日本でどのように扱われていますか?
現代の日本では、雑節は一般的な祝日とは異なりますが、地域によっては伝統的な行事や祭りとして引き継がれています。
特に農村地域では、農作業の節目として重要視されることが多く、地域のコミュニティーで集まり、共に祝うことがあります。
雑節はどのようにして決まるのですか?
雑節は、主に自然のサイクルや農作業の周期に基づいて決まります。
例えば、春の田植えの時期を告げる雑節や、秋の収穫を祝う雑節など、季節の変わり目や農作業の節目に合わせて設定されています。
そのため、年によって多少のズレがあることが特徴です。
雑節はどのような意味を持つのですか?
雑節は、自然や生活との調和を大切にする日本の文化を象徴しています。
季節の変わり目を意識し、自然のリズムに合わせた生活を送ることの重要性を教えてくれます。
また、地域コミュニティーを結びつけ、共に祝うことでコミュニケーションを深める役割も果たしています。
雑節に関する行事や食べ物はありますか?
はい、多くの雑節にはそれぞれ特有の行事や食べ物があります。
例えば、「端午の節句」では鯉のぼりを飾り、柏餅を食べる習慣があります。
また、「七夕」では笹の葉に願い事を書いた短冊を飾る習わしがあります。
これらは、雑節ごとの意味や歴史を反映した文化的な要素と言えるでしょう。
雑節と二十四節気の違いは何ですか?
雑節と二十四節気はともに季節の変化を示すものですが、その基準が異なります。
二十四節気は太陽の位置に基づいて定められ、一年を24等分したものです。
対して、雑節は自然の現象や農業のサイクルに基づくため、年によって日付が変わることがあります。
つまり、二十四節気はより定期的で予測可能な一方で、雑節は自然の変化により柔軟に設定される点が特徴です。
雑節はいつから日本で祝われていますか?
雑節は古来より日本で祝われており、その起源は古墳時代やそれ以前にまで遡ると考えられています。
農業が盛んになった時期から、作物の成長や収穫などに関連する様々な行事が生まれました。
これらは長い年月を経て、現代の日本でも一部地域で受け継がれています。
雑節に関する行事を祝うことの意義は何ですか?
雑節に関する行事を祝うことには、多くの意義があります。
まず、自然のサイクルを意識し、自然との調和を図るという環境に対する敬意があります。
また、地域の文化や伝統を守り続けることで、地域コミュニティーの絆を強める役割も果たしています。
これらの行事を通じて、歴史や文化の伝承も行われ、次世代に価値ある知識が受け継がれます。
雑節は他の国にも存在しますか?
雑節は日本独特のものですが、他の国にも季節の変化や農業のサイクルに合わせた祝日や行事が存在します。
例えば、中国には二十四節気があり、季節の移り変わりを示すものとして重要視されています。
また、西洋の国々には収穫祭など、収穫を祝う行事があります。
これらは各国の文化や自然環境に根ざした独自の伝統を反映しています。
現代日本において雑節を学ぶことの価値は何ですか?
現代日本において雑節を学ぶことには多くの価値があります。
まず、日本の歴史や文化を深く理解する手がかりとなります。
また、自然のリズムに敏感になり、環境に対する意識を高める機会となるでしょう。
さらに、地域の伝統や行事を知ることで、コミュニティーに対する理解を深め、世代間のつながりを強化することもできます。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は雑節についての情報をまとめました。
馴染みが薄い雑節もどのような意味があるのかをある程度理解すればそこから日にちも特定できるようになっています。
しかし、社日や土用のような特殊なものもありますので、それらは由来なども含めて覚える必要があるでしょう。
それ以外は二十四節気に比べると覚えやすいので丸暗記が得意な人ならば直ぐに覚えられるようになっています。

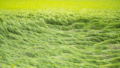

コメント