二十四節気における季節を表す表現の中に「清明」と呼ばれるものがあります。
今回は、2024年の清明はいつになるのか、時候の挨拶として使う「清明の候」とはどのような意味があるのか、正しい使い方について、そしてその時期に適した食べ物についても調べてまいります。
ポイントとなるのはもちろん二十四節気なので、こちらの仕組みを覚えられるような内容でお送りします。
清明の意味や由来は?

清明は二十四節気において太陽黄経が15度から30度になるまでの季節の事です。
この言葉は「清浄明潔」という「草木が芽吹きすべての生き物が清らかで、様々な巣類が明らかになる時期」という意味があり、春の訪れを伝えてくれる単語となっているのです。
二十四節気において同じように春に該当する啓蟄の場合は「地中にいた虫が出てくる時期」という意味があるので、そちらと比べると清明のほうがより活動的な意味があるといえるでしょう。
1787年に江戸で出版された暦に関する解説書である「こよみ便覧」によると、この清明の時期は「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり」という表現をされているとのことです。
また、二十四節気をより細かく分けた七十二候ではそれぞれの二十四節気を初候と次候と末候の3つずつに区分けしており、清明はそれぞれ初候が「玄鳥至(つばめきたる)」、次候が「鴻雁北(こうがんかえる)」、末候が「虹始見(にじはじめてあらわる)」という表現をしているのです。
どういうことかというと、最初は燕が渡ってきて、次は雁が北に帰り、最後に虹がよく見られるようになるという意味です。
2024年の清明はいつ?

「清明」という単語を聞くと日本人なら安倍晴明を思い出してしまいそうですが、そもそも漢字が違います。
このように勘違いされることも非常に多い清明ですが、時期は二十四節気において春分が終わった次のタイミングとなります。
具体的に2024年では4月4日からが清明となるのです。
二十四節気では大きく分けて季節を4つに分けていますが、春に該当する部分は立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨の6つとなっているので、今回紹介する清明は春の5番目の季節となっています。
清明の候の意味と正しい使い方は?

時候の挨拶で「清明の候」というものがありますが、もともとこの「候」は「~の季節」とか「~の天候」という意味がありますので、簡単な意味は「清明の季節に」という表現になります。
もっとかみ砕いて説明すると「草木が芽吹いて様々な種類が見分けられるような季節になりました」という表現になるのです。
ただし、使える期間というのはこの清明の時期のみとなりますので、2024年では4月4日から18日が該当します。
これらの時候の挨拶は二十四節気に密接にかかわっているので、使うタイミングがわからないという人は二十四節気がどうなっているのかを確認してください。
よくある定型文で「○○様にはますますご清祥のことと存じます」という表現がありますが、こちらに時候の挨拶をくっつければ挨拶として問題なく使えるでしょう。
ただし、これらの文章は堅苦しすぎるとそれはそれで嫌われることもありますので、ある程度仲がいい人には表現をいくらかかみ砕いたものを用意するといいでしょう。
ここら辺は受け取る側の気持ちを察する機微が重要になってしまいます。
清明節に行われる風習は?

日本において清明節に行われる風習はほとんどありません。
しいて言うなら、桜が咲いているのでお花見をするぐらいでしょう。
これが華人の場合は大きな意味を持つ季節となります。
清明節になったら祖先の墓参りをするという風習が中国では存在するのです。
いわゆる、日本でいうところのお盆や彼岸や年末年始でのお墓参りが中国では4月の清明節となっています。
華人はこの清明節になったら先祖のお墓に行って墓の掃除をして紙で作ったお金を墓前で燃やすといった行動をとる方が今でも非常に多くなっております。
それ以外に古代中国から始まった風習として清明節には緑豊かな郊外へピクニックにいくというものがあり、これは「踏青」と呼ばれるものだそうです。
あとは清明節には火を焚いてはいけないという風習も中国では残っています。
これは2500年前の春秋戦国時代における晋の国王の息子が暗殺を逃れるために逃亡生活をして、餓死寸前だったところをとある側近に助けられ、そこから数十年後にその恩を返そうと山で探したところ、火で綿山を燃やせば下山すると考え、それでもその側近が下山せず命を落としてしまったことに由来します。
この火事によって失われてしまったことを悲しんだ晋の皇帝はその時期が清明節の前日だったので、翌年から清明節では火を使った行いは禁止とされ、冷めた食事を摂取する習慣が始まったといわれております。
実際に清明節になると火を使わない料理を食べる風習が残っている地域があるとのことです。
清明の時期の食べ物は?
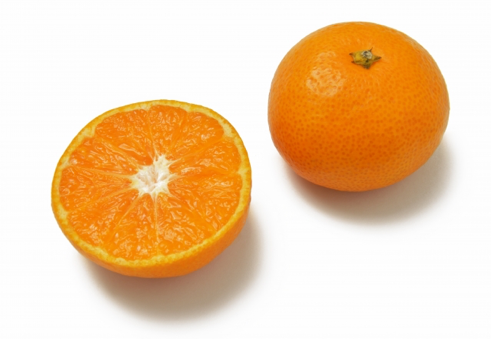
華人の場合はこのように清明節にはいろんなイベントがあるので、冷たい食べ物といった限定されたものを食べる必要がありますが、日本ではそのようなイベントはほとんどありませんので特に気にする必要はないでしょう。
とりあえず4月の旬のものを食べるのが正解となります。
4月の旬な食べ物は清見といったオレンジやミカンの中間と言われる果物や、いちご・あまなつ・キウイ・グレープフルーツ・デコポン・マンゴーといった果物が該当します。
野菜ならばアスパラガスやキャベツやゴボウやセロリ玉ねぎやレタスあたりが該当するでしょう。
タケノコや椎茸やきくらげあたりも旬なのでお勧めできます。
毛ガニやホタルイカといった海産物も旬になるので、海産物好きにも好まれるシーズンでしょう。
「清明」を持つ花の名とその花言葉は?

清明の時期はお花見シーズンなので桜を強くイメージする人も多いので、「清明を代表する花=桜」という結論に至っている人も多いです。
実は花言葉で「清明」という意味を持っている花があるのです。
それがキンポウゲ科デルフィニウム属の花である「ヒエンソウ」です。
このヒエンソウにはヒエンソウ・オオバナヒエンソウ・セリバヒエンソウの3種類が存在するのですが、日本で一般的に知られているヒエンソウはオオバナヒエンソウとなっております。
この花は蕾がイルカに似ていることからギリシア語でイルカのデルフィという言葉が属になっており、イルカと結び付けられれば覚えやすいでしょう。
清明に関するよくある質問まとめ
「清明」とは、具体的にはどのような時期を指すのでしょうか?
「清明」とは、二十四節気の中の第5番目の節気を指します。
毎年4月4日から4月6日頃にかけての時期を指し、この時期は春の中盤となり、自然が生き生きとし、天気が晴れやかで清らかになることからこの名がつけられました。
「清明」の名前の由来や意味について教えてください。
「清明」は、文字通り「清らかで明るい」という意味を持ちます。
この時期は、冬の終わりから春へと移行し、大気が澄み渡り、自然が鮮やかになることから、このような名前がつけられました。
「清明」の時期には、どのような伝統的な行事や風習があるのでしょうか?
「清明」は、特に中国では「清明節」として知られ、先祖の墓参りやお墓の掃除を行う日として重要視されています。
この時期には、家族で墓地を訪れ、故人を偲ぶ風習があります。
「清明」の時期の天候や気候の特徴を教えてください。
「清明」の時期は、春の中盤となるため、徐々に暖かくなってきます。
しかし、まだ寒暖の差があり、昼夜の気温差も大きいことが特徴です。
春の草花が一層美しく咲き誇る時期でもあります。
「清明」に関連する言葉や四字熟語、詩などはありますか?
「清明」に関連する詩として、古くから多くの詩が詠まれています。
特に、唐の詩人である杜牧の「清明」という詩が有名で、「清明の時節雨紛紛、路上の死人魂独り」という一節で始まる詩として知られています。
「清明」とは何のための節気なのでしょうか?
「清明」は春の中盤の節気で、自然界の変化や農作業の目安として古くから使用されています。
特に、この時期は種まきや畑仕事が盛んに行われ、春の農作業のピークを迎える重要な時期となります。
「清明」の時期の食材や旬のものにはどのようなものがありますか?
「清明」の時期には、新緑の野菜や春の山菜が豊富になります。
特に、タラの芽やわらび、こごみなどの春の山菜が旬を迎え、これらを使った料理が各地で楽しまれます。
「清明」は日本だけの節気なのでしょうか?
いいえ、「清明」は日本だけでなく、中国や韓国、ベトナムなどの東アジア諸国でも認識される節気の一つです。
特に中国では「清明節」として、先祖の墓参りの日としての重要性が強調されています。
「清明」の時期に気をつけるべき健康のポイントはありますか?
「清明」の時期は春の中盤で、気温が上昇する一方で、まだ寒暖の差が大きくなる日もあります。
このため、体調を崩しやすくなることがあるので、適切な服装や食事、十分な睡眠を心掛けることが大切です。
「清明」に関することわざや故事成語は存在するのでしょうか?
「清明」に関連することわざとして、「清明の雨水」という言葉があります。
これは「清明」の時期に降る雨のことを指し、春の雨の恵みを表現したものです。
また、故事成語として直接的なものは少ないですが、清明節に関連する文化や習慣から生まれた言葉や故事も存在します。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は清明についての疑問を解消するために様々な情報を集めてまいりました。
あまりなじみのない季節である清明ですが、春分といった日本でもなじみがある季節と絡めると比較的覚えやすいのでこの有名な季節と結び付けるようにしましょう。
日本ではイベントがほとんどない季節ですが、中国では非常に重要な季節となっているので知り合いに華人の方がいる方は覚えておくと役立ちます。
清明以外の二十四節気一覧はこちら!

今回は清明についてたくさん解説してきましたが、他にも二十四節気が23個も存在しています。
23個と聞くとかなりの数ですよね。
ここでは清明以外の二十四節気についてご紹介したいと思います。
それぞれどんな特徴があるのか見てみましょう。



コメント