「立冬の候」といった使い方をする二十四節気の一つである立冬ですが、この立冬はいつから始まるのか答えられる人は少ないでしょう。
今回は2023年の立冬がいつからなのか、そもそもの意味や由来は何なのか、その時期の食べ物や「立冬の候」の使い方などの情報をまとめていきます。
後半では立冬以外の二十四節気についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
立冬の意味や由来は?
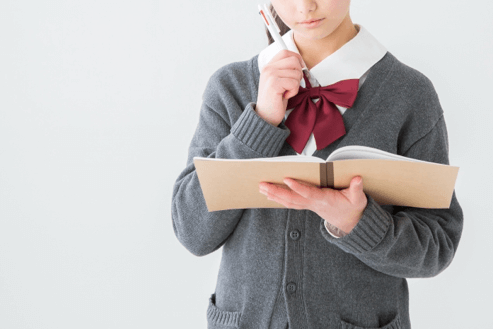
立冬は「冬が始まる」という意味があります。
中国語における「立」という漢字は始まりを意味しているので、非常にわかりやすいでしょう。
また、日本の暦解説書である1787年に出版された暦便覧によると、この立冬は「冬の気立ち初めていよいよ冷ゆれば也」という表現をされています。
「冬の気配が立ち始めてだんだん冷え込んでくるから立冬なのである」という意味で、日本でも冷え込みがきつくなるシーズンというイメージが当時からあったようです。
しかし、現代日本人にとっては「11月の上旬が冬の始まりといわれてもあまりイメージできない」とか「ちょっと早すぎるのでは?」という否定的な言葉が出てきてしまうことが多いでしょう。
これが非常に厄介なことなのですが、二十四節気における冬は「立冬⇒小雪⇒大雪⇒冬至⇒小寒⇒大寒」の6つの節気になっているのに、気象庁の冬は12月から2月となっているので、イメージがずれてしまうのです。
祝日は二十四節気にあやかっているのに、季節のイメージは気象庁の発表のほうにあやかっていることが多いので、二十四節気の説明と日本人のイメージはかなりの乖離が発生します。
このずれをずらすために二十四節気を日本向けの解釈を加えてさらに3分割した七十二候も用意されていすが、やはり多少ずれていると感じてしまうことがあります。
2023年の立冬はいつ?

2023年の立冬は11月8日から21日までです。
もともと、この二十四節気は太陽が星座間を移動する道である黄道を、360度に分けたものが黄経を基準に考えられているので、正確に星の位置を観測できる機関の報告が求められているのです。
また、春分点が0度となっていますので、この立冬は225度から240度とだいぶ進んだ位置になるのです。
ちなみに、冬を表す二十四節気は立冬⇒小雪⇒大雪⇒冬至⇒小寒⇒大寒となっておりますので、覚えておくといいでしょう。
立冬の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?
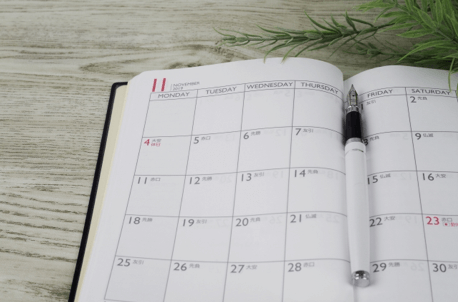
時候の挨拶として用いられる「立冬の候」というのは「立冬の季節でございます」といった丁寧な言葉となります。
もともと「候」は季節を表す言葉でもありますが、「~である」を丁寧にした表現でもあるので、どちらの意味でとらえてもこのような表現となるのです。
ただし、この時候の挨拶は二十四節気のタイミングを理解したうえで使う必要があるので注意しましょう。
メールのようにタイムラグがほとんどなく送信できる文章ならばいいのですが、手紙といった到着までにタイムラグがあるものにこの時候の挨拶を用いると、1日か2日のずれで時候の挨拶そのものもずれてしまうケースもあるので、その場合は別の挨拶を用いたほうが安全なのです。
立冬の三候について

七十二候とは古代中国で考案された二十四節気をさらに3つに分けた期間のことです。
基本的に二十四節気は約15日で一区切りとなっていますので、七十二候は約5日で一区切りとなっています。
そして、この七十二候はちょっとした短文形式となっており、その時の季節の様子を動物や環境がどうなっているのかを表現することで示しております。
ただし、古代中国の七十二候は日本の風土とは合わないところもしばしばあるので、江戸時代に入ってから渋川春海といった暦学者たちが日本向けのアレンジを行っています。
なので、ここではその日本向けにアレンジされた七十二候を見ていきましょう。
まずこの七十二候は初候・次候・末候の3段階があり、それぞれ「山茶始開(つばき はじめて ひらく)」「地始凍(ち はじめて こおる)」「金盞香(きんせんか さく)」という表現がされています。
つまり立冬とは「山茶花が咲き始めて、大地が凍り始め、そして水仙の花が咲く季節」という表現をされているということです。
山茶花は場所や種類によっては10月に咲くことがありますが、11月に咲くことが多いので七十二候として用いられるのも納得です。
水仙は冷え込むことが多い場所ならば早いと12月に咲くでしょうが、今の日本だと1月や2月、種類によっては3月に咲く花なのでちょっとここの表現はイメージがしくいかもしれません。
問題は大地が凍るという表現で、「11月は寒いけど氷点下にまではいかない」という突っ込みをしたい方も多いでしょう。
この部分は日本が当時と比べると温かくなったと考えて切り替えるしかありません。
立冬の時期の食べ物は?

立冬は11月中旬の時期になりますので、その時旬な食べ物が代表する食べ物と言えるでしょう。
具体的には野菜だとカボチャ・カリフラワー・ごぼう・春菊・大根・チンゲン菜・長ネギ・ニンジン・野沢菜・白菜・ブロッコリー・ほうれん草・ゆりね・ルッコラ・レタス・レンコンなどが該当します。
ジャガイモやサツマイモや里芋といった芋類も旬です。
果物ですと、リンゴを筆頭に柿・ゆず・キウイ・ミカン・かりんあたりが旬となります。
魚はかなりの種類が旬となり、はまち・カマス・キチジ・こはだ・サケ・サバ・鰆・シシャモ・タチウオ・ニシン・ハタハタ・鱧・ヒラメ・ふぐ・ボラなどが旬となります。
タラバガニや毛ガニやイセエビやイクラといった海産物も旬となりますので、海産物好きは過ごしやすいでしょう。
立冬の季節の花は何?
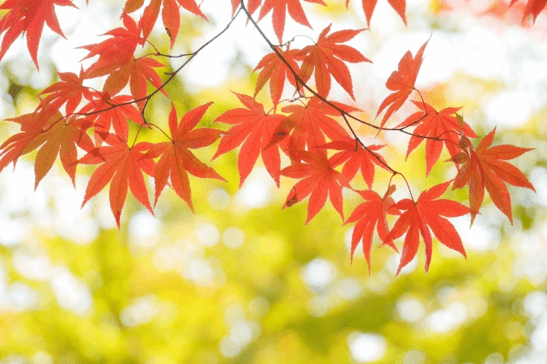
11月中旬に綺麗に咲く花および咲いている花はいろいろとありますが、代表的な花は山茶花・シクラメン・ポインセチア・エリカ・アロエ・コスモス・バラ・サルビアあたりでしょう。
七十二候で紹介した山茶花も綺麗に咲きますので、この立冬を代表する花と言えるのではないでしょうか。
立冬以外の二十四節気一覧を紹介!

今回は立冬について詳しく解説してきましたが、文字通りあと23個の二十四節気が存在していることはご存知でしょうか?
ここでは立冬以外の二十四節気についてまとめましたので、ぜひご覧ください。
それぞれにいろんな意味がありますので、調べてみると面白い内容になっていますよ。
立春
雨水
啓蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小満
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
処暑
白露
秋分
寒露
霜降
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
立冬に関するよくある質問まとめ
「立冬」は具体的にはいつ頃を指すのですか?
「立冬」は、二十四節気の中で冬の始まりを意味する節気で、毎年11月7日頃に訪れることが多いです。
この日を境に、日本の多くの地域で冬の訪れを感じるようになります。
「立冬」という名称の意味や由来は何ですか?
「立冬」とは、文字通り「冬が立つ(始まる)」という意味を持っています。
古代中国の太陽暦に基づいた節気の一つとして、「立春」や「立夏」などと同じく、季節の変わり目を示すものとして名付けられました。
「立冬」の時期に行われる伝統的な行事や風習はありますか?
「立冬」の頃には、冬の寒さを乗り越える力をつけるという意味で、よもぎやにんにくを入れた「立冬の汁」を飲む風習がある地域もあります。
また、この時期には新米の収穫が行われ、新しい収穫を祝う行事や食事も多く行われます。
「立冬」の季節の特徴や気象にはどのようなものがありますか?
「立冬」を迎えると、気温が急激に下がり、初雪を迎える地域も出てきます。
日照時間が短くなり、乾燥する地域も多く、スキンケアや加湿対策が必要となる季節となります。
「立冬」の時期に気をつけたい健康上のポイントはありますか?
「立冬」の時期は、急な気温変動や乾燥により、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。
また、乾燥した空気はのどや肌にも影響を及ぼすため、十分な保湿やうがい、手洗いの習慣を心がけることが大切です。
「立冬」の日に特別な料理や食材を摂取することはありますか?
「立冬」の頃には、体を温める効果があると言われる食材や料理が注目されます。
具体的には、ジャガイモやさつまいも、ねぎや生姜といった食材を中心とした料理が好まれることが多いです。
これらは寒さを乗り越えるためのエネルギー源として、また風邪の予防としても効果的です。
「立冬」は他の国や文化でも意味があるのですか?
「立冬」はもともと中国の節気から来ており、中国や韓国、ベトナムなどの東アジア諸国でも類似の意味を持つ節気として認識されています。
各国で微妙に日付や風習が異なることもありますが、共通して冬の訪れを感じ取る節目として位置づけられています。
「立冬」と「小寒」や「大寒」とはどのように関連していますか?
「立冬」は冬の始まりを示す節気で、次に来る「小寒」は冬が本格的に深まることを示し、「大寒」は年間で最も寒さが厳しくなる時期を指します。
これらの節気は、冬の進行を示す目安として、農作業や生活の中で大切にされてきました。
「立冬」の時期におすすめのアクティビティや過ごし方はありますか?
「立冬」の頃は、冬の訪れを感じながらの自然散策や、温泉でのリラクゼーションがおすすめです。
また、この時期からの冬のイベントやフェスティバルの情報をチェックし、計画的に楽しむのも良いでしょう。
家では、冬の味覚を楽しむ料理やホットドリンクを準備して、ゆっくりと過ごすのも良いと思います。
「立冬」に関する言い伝えや昔話はありますか?
「立冬」には様々な言い伝えや昔話が伝わっています。
日本の一部の地域では、「立冬の日に大根を食べると風邪を引かない」という言い伝えがあり、大根料理を食べる家庭も多いです。
また、昔話や伝説の中にも「立冬」をテーマにしたものが存在し、季節の変わり目の大切さや自然との関わりを感じることができます。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は立冬についての情報をまとめました。
立冬は冬が始まるという意味ですが、日本人的にはイメージしにくいのは致し方ないでしょう。
日本人的には12月から2月までが冬というイメージが強く気象庁もそのように扱っているので、二十四節気的な考え方がどうもマッチしないのです。
それでも覚えたいという方は、冬至や夏至といった有名な二十四節気を基準に考えるようにしてください。



コメント