二十四節気の中に「立秋」がありますが、いつなのか、よく使われる時候の挨拶である立秋の候とはどんな意味があるのかよくわからないと感じてしまうことがあります。
そこで、今回は立秋の候とはなんなのか、そもそも立春の意味や由来は何なのか、その時期に旬となる食べ物は何なのかをお答えいたします。
旬な食べ物とセットで覚えるとかなり簡単に覚えられるのでお勧めですよ。
立秋の意味や由来!

江戸時代の1787年に出版された暦の解説書である「暦便覧」によると、立秋とは「初めて秋の気立つがゆへなれば也」という言葉で表されています。
要するに「秋の気配がする時期」ということです。
この立秋の時期に突入すると、「暑中見舞い」の時期は終わり「残暑見舞い」の時期になりますので、贈り物を出すタイミングには注意してください。
また、梅雨明けのタイミングがなくズルズルとずれ込んで立秋にまで到達してしまった場合は梅雨明け宣言がなくなります。
このように秋の訪れを感じるタイミングから「立秋」となっていますが、日本人的な感覚では「秋の訪れなんかまったく感じない」とか「夏休み真っただ中でものすごく暑いのに秋といわれても困る」という冷静な突っ込みが返ってくるでしょう。
このようにイメージと大きくずれてしまっているのは、もともとこの二十四節気の発祥となっている中国の洛陽周辺の気候と日本の気候が大きく異なっているからです。
平均気温が下がり始めたら「夏が終わった」とか「秋が始まった」というイメージを持ちやすいのですが、日本の8月は日本の中で最も熱くなることが多いので「夏が終わった」というイメージよりも「夏真っ盛り」とか「最も熱くて寝苦しい時期」というイメージのほうが圧倒的に持たれるようになっています。
2024年の立秋はいつ?

2024年における立秋とは8月7日から8月22日までとなっております。
様々なところでこの日程については報告していますが、最も信頼しているところから情報を集めたいという方は国立天文台発表の二十四節気を確認するといいでしょう。
中央標準時における日にちだけではなく正確な「〇時○○分」という記載までしてあるのです。
より細かく記載すると、もともとこの二十四節気とは太陽が星座間を移動する道である黄道を24分割、すなわち15度毎に分割して表現したものとなっており、今回紹介する立秋とは春分点を起点としたときに135度に来たところとなります。
立秋の候の使い方、いつからいつまで使えるの?
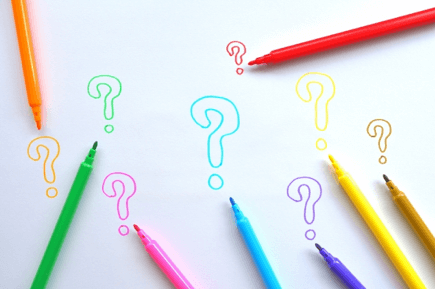
メールや手紙で用いられる様々な時候の挨拶の中に「立秋の候」という表現があります。
時候の挨拶でイメージができないという人は「秋たけなわの頃」とか「残暑厳しき折」といった表現と同じと考えてください。
この「立秋の候」とは「立秋の時期」とか「立秋のおり」という表現に言い換えることができて、もっと簡単に記載すると「立秋でございます」というかしこまった表現となるのです。
この「立秋の候」という時候の挨拶は立秋のタイミングでしか使えない期間限定の言葉となっているので注意してください。
同じように二十四節気は時候の挨拶として用いることができますが、それぞれその二十四節気のタイミングでしか使えないようになっていますので、先ほど紹介した国立天文台の発表と照らし合わせながら記載するようにしましょう。
立秋に行われる風習は?

立秋のタイミングで行われる風習として今でも根強く残っているのはお盆でしょう。
どのような会社でもお盆のタイミングは休みになることが多く、日本人にとってまとまった連休が取れるシーズンでもあります。
お盆とは亡くなったご先祖様が地上に戻ってくる期間であり、その亡くなった方々を迎えて感謝と供養を行う期間でもあるのです。
地方によってこの風習やマナーは多少異なっていることがありますが、基本的には8月13日がご先祖様を迎える日であり、16日がお見送りの日となっています。
会社のお盆休みもこの13日から16日に設定されていることが多く、これに土日が絡んでくると長期の休み期間になることが多いのです。
この時期になると仏壇があるお家は綺麗に掃除をするようになりますので、しっかりと掃除してあげてください。
また、菓子折りや果物をお供えするときは熨斗紙を使ってはいけません。
もともと、この熨斗紙はアワビの肉を薄くはぎノシアワビの代わりに浸かっているものであり、このアワビが殺生をイメージさせることから弔事や不祝儀に用いることはNGであるという考え方が残っているのです。
今ではこのような風習を守っている人もかなり少なくなって、お盆の期間は仕事で疲れた社会人にとっては「ちょっとした夏休み」ぐらいのイメージしか持っていないことが多々ありますが、ご先祖様を思える数少ないタイミングなので、仏壇がない人でもお祈りや墓参りはしましょう。
立秋の時期の食べ物は?

立秋の時期はお盆と被っているので、お盆のルールをまず覚えるべきでしょう。
基本的にお盆は「無駄な折衝はしてはいけない時期」とか「豪華絢爛な食事をしてはいけない時期」という風習が残っているので、精進料理を食べる人もいます。
ただし、この風習はかなりすたれているのでお盆のタイミングだからといってこれらのルールを順守している人は少なくなっているのも事実です。
この考え方は地方や家庭ごとに異なりますので、その地域に合わせたほうがいいでしょう。
特に気にしないという人は好きなものを食べて問題なしです。
仏教ではお盆期間は無駄な殺生を避けるという風習が残っていますので、この時期は夏野菜やいなりずしやうどんやそうめんや白玉団子が食べられやすくなっています。
白玉団子には浄土へのお土産になるという考え方が残っていますし、細くて長いそうめんには長生きする縁起物という考え方が残っているのです。
トウモロコシやカボチャやキュウリやトマトやナスといった旬の野菜は豊作を祈願するお供え物として使われることもあります。
立秋の季節の花は何?
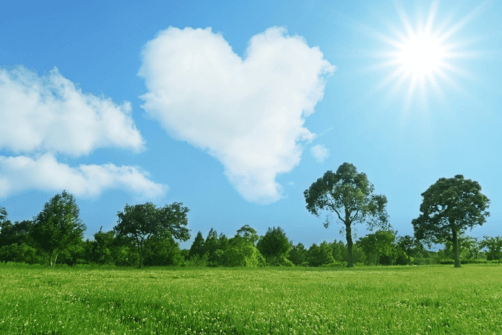
立春は8月中旬に該当するのでその時期に美しく咲く花が季節の花となるでしょう。
具体的にはヒマワリ・サルビア・朝顔・ユリ・スイレン・ダリア・コスモスなどが該当する花となります。
特に夏を代表するヒマワリなどは大きく花開きますので、美しい姿を見ることができるでしょう。
立秋に関するよくある質問まとめ
「立秋」は一年の中でどの時期に設定されていますか?
「立秋」は二十四節気の一つで、毎年8月7日から9日頃に設定されています。
この時期は、夏から秋への移行を象徴し、一年の中で夏の終わりを迎える時期となります。
「立秋」という名前の由来や意味は何ですか?
「立秋」の「立」とは「始まる」という意味を持ち、秋が始まることを示しています。
従って、「立秋」は秋の始まりを意味する節気で、この日を境に日が短くなり、涼しさを感じることが増えてきます。
「立秋」の頃の日本の風物詩や行事はありますか?
「立秋」の頃は、多くの地域で夏祭りや盆踊りが行われ、夏の終わりを楽しむ風物詩として親しまれています。
また、この時期は稲の収穫も近づくため、田んぼの風景も見頃となります。
「立秋」に関連した食材や料理はどのようなものがありますか?
「立秋」の頃に旬を迎える食材としては、栗やサンマ、柿などが挙げられます。
特にサンマは秋の代表的な魚として知られ、この時期の味覚を堪能することができます。
「立秋」に特有の天候や気象の変化はどのようなものがありますか?
「立秋」の頃から、日中の高い気温とは対照的に、朝晩の気温が低くなる傾向が見られます。
また、秋の夜長を感じさせるような涼しい風が吹くことが多くなり、梅雨の湿度も落ち着き、過ごしやすい気候となります。
「立秋」の後に続く二十四節気は何ですか?
「立秋」の後に続く二十四節気は「処暑」(しょしょ)です。
これは、最も暑い期間が終わり、次第に涼しさが増してくることを示しています。
立秋の日にはどのようなことをすれば良いと言われていますか?
「立秋」には、健康を意識した行動をとることが推奨されることが多いです。
例えば、季節の変わり目に体調を崩しやすいため、早寝早起きを心掛けたり、旬の食材を取り入れた食事を摂るなど、体調管理に気を付けると良いでしょう。
立秋の頃の月はどのような姿を見せるのでしょうか?
「立秋」の頃の月は、お盆を迎える頃とも重なるため、満月に近い明るい月を楽しむことができます。
この明るい月の下での盆踊りや夏祭りは、日本の夏の風物詩として多くの地域で楽しまれています。
立秋の時期は風邪を引きやすいとよく言われますが、その理由は何ですか?
「立秋」の頃は、日中の気温と夜間の気温の差が大きくなることが多いです。
この急な気温変化に体が慣れないため、免疫力が低下しやすくなることが、風邪を引きやすくする主な理由とされています。
二十四節気の中で、「立秋」はどの位置にあたるのでしょうか?
二十四節気の中で、「立秋」は13番目の節気となります。
前の節気は「大暑」となり、次の節気は「処暑」と続いていきます。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は立秋について詳しく紹介いたしました。
立秋はお盆のタイミングと完全に一致していますので、時期がわからないという人はお盆とイメージを合わせてもらえればいいでしょう。
食べ物についての制限はその人の住んでいる地域や家庭環境によって変わりますので、家族と住んでいる方々は暇なときに確認することを強くお勧めします。
立秋以外の二十四節気はこちら!

今回は立秋の意味や由来、立秋の候などについて詳しく解説してきましたが、立秋以外の二十四節気はあと23個も存在しています。
これを機に残り23個の二十四節気についても見てみませんか?
それぞれの意味を理解して日々の生活に役立ててみてください。

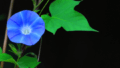
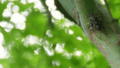
コメント