日本でもなじみが深い立春ですが、具体的に立春になんかをすると決めて行動する人は少ないでしょう。
今回は、2024年の立春はいつなのか、立春大吉でお札を貼る意味とはいったい何なのか、そもそも立春の由来は何なのか、この立春に食べる食べ物で縁起がいいのは立春朝搾り以外に何があるのかといった疑問を解消するべく記載してまいります。
お祝い事に対する考え方が非常に薄くなってしまった現代だからこそ、昔の風習をあえて調べることに大きな意味があるのです。
記事の後半では立春以外の二十四節気についても触れているのでぜひ最後までご覧ください。
立春の意味や由来は?

立春とは春の季節が始まるタイミングであり天球上における経度に該当する太陽黄経が315度になった日です。
昔は太陽の黄経が315度から330度になるまでが立春という扱いだったので、約15日間ほどは立春だったのですが、今では315度になったその日だけが立春という扱いになっています。
一応暦の上では「春がはじまる日」であり、冬至と春分のちょうど間に来る日でもあります。
覚えにくいという方は冬至と春分を覚えられれば連鎖して覚えられるでしょう。
ただし、この立春は旧暦の旧正月とは別物であり、地球と太陽の位置関係をもとに考えられた二十四節気の一つであり、太陰太陽暦を使った旧暦とは異なるのです。
つまり、立春とは二十四節気からきているので由来を調べるにはこちらの二十四節気を探る必要があります。
2024年の立春はいつ?

立春は、春の季節が始まるタイミングであり天球上における経度に該当する太陽黄経が315度になった日になります。
このように星の角度が関係している暦が存在しているので日本では国立天文台が毎年2月に翌年の暦要項を発表しているのです(具体的には春分や秋分や冬至といった祝日が密接に関係している)。
そちらを確認すると2024年における立春は2月4日です。
ちなみに、2025年の立春も2月4日なので一緒に覚えておくといいでしょう。
立春大吉とは?なぜお札を貼ったりするの?
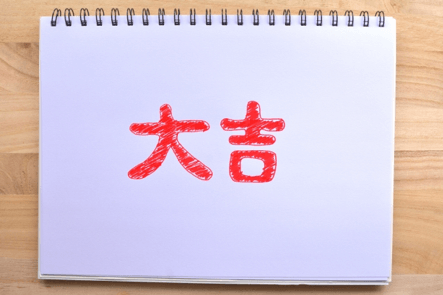
日本でもまだ残っている禅寺で、立春の朝に門に「立春大吉」と書いた紙を貼るという風習がはっきりと残っております。
このお札の意味は「古来の新年の始まりであった立春に社会や人々の幸せを祈願するため」というものがありますが、これを貼ると家の敷地に魔が入ってこないようになるといういわれがあります。
つまり、魔よけとして用いていたのです。
また、立春の前日にある節分とも大きくかかわっており、そこで発生する鬼が入ってこないようにするためという意味が込められています。
昔ながらの風習なので、今でも実行しているお寺や神社は昔ながらの風習がしっかりと残っているといえるでしょう。
出雲大社の相模分祠や奈良県にある春日大社の神社ではこのようなお札をもらうことができるので、定期的に貰いに行く人もいます。
立春と節分の関係は?

立春において重要になるお札は立春の前日にある節分とも大きくかかわっており、鬼が入ってこないようにするため、つまり魔除けに使えるというお話をしました。
鬼がそれでも入ってしまった場合、左右対称の「立春大吉」のお札を見て裏から「立春大吉」と呼んでしまい通っていないと勘違いして出ていってしまったという逸話もあります。
さらにここからマニアックなお話をしましょう。
先ほどの二十四節気と陰陽師でも有名な陰陽五行説は非常に絡み合っており、立春・立夏・立秋・立冬という季節の変わり目となるタイミングは非常に不吉なタイミングであり鬼が発生するといわれていたのです。
節分は季節の変わるタイミングで鬼を除外するために行われていた恒例行事の一つなのです。
この考え方は日本人にもいまだに深く根付いており、お正月に行われるしめ飾りやお正月飾りも季節の変わり目において発生する鬼や邪鬼が入ってこられないようにするための行事なのです。
立春にすることって何?

このように立春は鬼が入ってくるタイミングと考えられているので、先ほど紹介した「立春大吉」のお札を玄関に貼るというのも有効でしょう。
それ以外にも鬼門にあたる北東側に貼るとか、神棚や仏壇に貼ることも有効です。
貼るときは必ず大人の目線よりも上になるように注意して貼りましょう。
自分で和紙や半紙などを用意し墨で書いて貼るというやり方もありますし、お札のネット注文すら可能となっています。
処分するときはどんと祭りのタイミングで燃やすか神社や寺院の古札納所でお返しすることが重要です。
他にはこの立春のタイミングで朝一番にくんだ水は年の初めにくんだ水として「若水」と呼び、この水を使って食事の支度をするといったやり方でいいそうです。
この水で用意されたお茶は「福茶」と呼ばれており、こちらを飲むこともよい行いと言われております。
立春に食べる食べ物は?立春朝搾りって何?

立春で食べるものは朝一番でくんだ水を使った料理が一般的となっています。
このお水を料理に使う前に神棚にお供えしてから使うとより良いと言われています。
それ以外には立春の朝に搾りあがったばかりの酒を飲むと良いという風習もあります。
このお酒がいわゆる立春朝搾りと呼ばれるもので、一部のお店では立春朝搾りを販売しているところもあります。
それ以外には縁起がいいものを食べる習慣があり、昔から邪気を払う力が宿るといわれていたお豆腐は立春大吉豆腐として販売されることがあります。
また、餅が入っているまんじゅうを食べるのも縁起がいいとされており、立春大福や立春饅頭も食べられています。
いろんな和菓子が福をもたらすということでこの時期に食べることが推奨されているようです。
赤福で有名な和菓子店も立春のタイミングで立春大吉餅という名前の大福を販売しているので、興味がある方はのぞいてみましょう。
立春の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?

「立春の候」とは社会人になるとたまに使うことになるいわゆる「時候の挨拶」の一種です。
意味は「温かくなってくるこの頃」とか「春を感じる季節になってきたこの頃」といったものとなります。
時候の挨拶として用いられることの多いこの「候」は「~の季節」とか「~の天候」という意味があるので「立春の候」という言葉は「春になった季節」という意味にもとれます。
ただし、この時候の挨拶が使えるタイミングは立春開始日から2週間後の雨水と呼ばれるタイミングの前日であり、2月4日が立春ならば2月18日となるのです。
立春に関するよくある質問まとめ
「立春」とは具体的にどのような意味を持っていますか?
「立春」は、二十四節気の中で最初の節気として位置づけられています。
名前の通り、春が始まることを意味し、冬から春への移行期を示しています。
この時期は、新しい生命が芽吹き始める象徴的な瞬間とされています。
「立春」の時期に行われる伝統的な行事や風習はありますか?
「立春」の時期には、春を迎えるさまざまな行事や風習があります。
例えば、日本では「立春大吉」という言葉を聞くこともあり、この日に「恵方巻」を食べる風習がある地域も存在します。
また、新しい季節を迎えるための祈りや儀式も行われることが多いです。
「立春」はどのように日付が決まっているのですか?
「立春」の日付は、太陽が黄道上で天の赤道を北に渡る日として定義されています。
具体的には、太陽黄経が315度になる日が「立春」となります。
そのため、毎年2月4日または5日に訪れることが一般的です。
春と言えど「立春」の時期はまだ寒いのはなぜですか?
実際に「立春」が訪れても、多くの地域ではまだ寒さが残っています。
これは「立春」が太陽の位置に基づいて決まるため、気温や天候とは必ずしも一致しないからです。
そのため、「立春」は春の訪れを象徴するものの、実際の気温は地域や年によって大きく異なります。
「立春」の時期に特有の健康上の注意点は何でしょうか?
「立春」の時期は、昼夜の気温差が大きくなることが特徴です。
このような気温変動は、風邪を引きやすくする原因となります。
また、春になると花粉の飛散が始まる地域もあるため、花粉症の方は早めの対策を心がけるとよいでしょう。
「立春」の日に特定の食材を食べるという風習や習慣は存在しますか?
「立春」に関連する食の風習としては、日本では「恵方巻」を食べる習慣が有名です。
この恵方巻を無言で一気に食べることで、一年の無病息災と繁栄を願うとされています。
また、一般的には新しい季節の到来を祝うため、旬の食材を取り入れた料理を楽しむ地域も多いです。
「立春」にはどのような風物詩がありますか?
「立春」は、冬から春への移行を象徴する節気です。
この時期になると、梅の花が咲き始めたり、日が長くなり日の出が早くなるなど、春の訪れを感じさせる風物詩が多く見られます。
また、鳥たちの鳴き声も活発になり、春の訪れを告げています。
「立春」は他の国や地域でも祝われていますか?
二十四節気は、中国を起源とするもので、その後、日本や韓国、ベトナムなどの東アジア地域に広がっています。
「立春」もこれらの国や地域で認知されており、それぞれ独自の風習や行事が行われています。
具体的な風習は地域によって異なりますが、共通して春の訪れを祝う意味合いがあります。
なぜ「立春」は春の始まりとされているのですか?
二十四節気は、太陽の動きを基にして定められています。
「立春」は太陽黄経が315度になる時点で、これは天の赤道を太陽が北上する時点を示しています。
この太陽の動きは、自然界の生物が春の訪れを感じ取り、活動を開始する時期と一致しているため、春の始まりとされています。
「立春」の時期に身につけると良いとされる色やアイテムはありますか?
「立春」は新しい季節の始まりを迎える節気であり、新しいスタートを意味するとされています。
そのため、新しい服やアクセサリーを身につけることで、新しい季節のエネルギーを取り入れると言われています。
特に緑や桃色は春を象徴する色とされ、この時期に身につけると良いとされています。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は立春についての気になる情報を集めてまいりました。
立春にまつわるこれらの行事を今でも行っている人は少ないでしょう。
しかし、昔ながらのお店やお寺や神社はこの風習がしっかりと残っているので確認してみると色々と発見があります。
気になる方はすぐにチェックしてみましょう。
立春以外の二十四節気一覧はこちら!

今回は立春について詳しく解説してきましたが、他にも23個の二十四節気が存在します。
これを機に立春以外の二十四節気についても学んでみませんか?
知らなかったことをたくさん学べると思いますよ。
それでは一覧をみていきましょう!


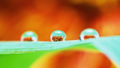
コメント