霜降は時候の挨拶として使うこともありますが、そもそもの読み方を含めてわからないことのほうが多いという人もたくさんいます。
そこで、今回はこの霜降の意味や由来、2023年はいつなのか、霜降の時期の旬な食べ物や時候の挨拶として使う「霜降の候」の扱い方などを記載してまいります。
夏至や冬至といった日本でも知られている二十四節気と絡めて覚えていきましょう。
霜降の意味や由来

霜降は1787年(天明7年)に江戸で出版された暦の解説書である「暦便覧」によると、「つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也」という表現をされています。
わかりやすく解説すると「朝露や夜露が気温の低下により霜が降りてくる季節」ということです。
霜が降りる季節となるとだいたい0℃くらいなのでかなり寒いのですが、それだけ寒さが近づいている季節なのでしょう。
より日本の季節に合わせた表現になっている二十四節気を三分割した七十二候の表現を見てみるとよりわかりやすくなります。
この七十二候は初候・次候・末候の3つに分かれておりますが、それぞれ初候が「霜始降(しも はじめて ふる)」、次候が「霎時施(こさめ ときどき ふる)」、末候が「楓蔦黄(もみじ つた きばむ)」となっております。
こちらをわかりやすく解説すると「霜が降り始めて、小雨がしとしと降り、もみじや蔦が黄葉する季節」となっております。
この七十二候の表現のほうがよりわかりやすいのでこちらのイメージを優先するようにしましょう。
一気に寒くなってくるシーズンとなっていますので、体調管理には十分に気を付けて服を選ぶようにしてください。
2023年の霜降はいつ?正しい読み方は?

2023年における霜降は国立天文台の発表によると10月24日から11月4日までとなっております。
この「霜降」の読み方は「そうこう」となっていますので、覚えておきましょう。
霜降は秋を表す二十四節気の一つで、順番としては「立秋⇒処暑⇒白露⇒秋分⇒寒露⇒霜降」となっているので6番目と言えるでしょう(立春を1番目とするなら18番目)。
基本的に二十四節気の一つの節気はだいたい15日が期間となっていますので、秋分の約1ヶ月後から霜降が始まると言えるでしょう。
霜降の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?
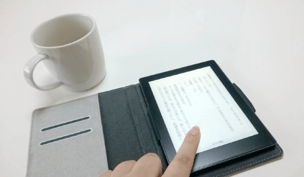
朝と夕方の気温が一気に下がってくるシーズンの霜降は時候の挨拶として「霜降の候」という使い方ができます。
ざっくりとした意味は「霜降の季節になりました」となりますし、もっとかみ砕くと「秋が深まって霜が降り始める季節になりました」という表現になるでしょう。
使えるタイミングは二十四節気の霜降に該当する時期のみなので、手紙を出すときは注意しましょう。
メールならば送ったらすぐに相手に確認されるものですが、手紙の場合は到着までのタイムラグによって節気が移り変わっている可能性があるので、時候の挨拶として使えなくなっているケースもあるのです。
これ以外にこの時期に使える時候の挨拶は「秋麗の候」や「錦秋の候」というものがありますので、二十四節気の移り変わりそうなタイミングだった場合はこのように別の時候の挨拶を使うようにしましょう。
霜降に食べる食べ物は?

霜降には柿を食べると風邪をひかなくなるという考え方が残っていますが、この時期に決まって食べなければいけないものというのは特にありません。
10月下旬と11月上旬をまたがっているこの霜降で旬となる食べ物は、野菜だとカボチャ・ごぼう・春菊・大根・チンゲン菜・長ネギ・ニンジン・野沢菜・白菜・ブロッコリー・ほうれん草・ゆりね・ルッコラ・レタス・レンコンなどが該当します。
ジャガイモやサツマイモや里芋がおいしい時期でもあります。
果物ですと、リンゴを筆頭にゆず・キウイ・ミカン・柿あたりが旬となります。
魚はかなりの種類が旬となり、はまち・カマス・キチジ・こはだ・サケ・サバ・鰆・シシャモ・タチウオ・ニシン・ハタハタ・鱧・ヒラメ・ふぐ・ボラなどが旬となります。
タラバガニや毛ガニやイセエビやイクラといった海産物も旬となりますので、海の幸がおいしい時期ともいえるでしょう。
霜降の時期にある風習は?

霜降の時期にある風習は紅葉狩りや霜対策でしょう。
二十四節気の説明で霜という単語が何度か出てきましたが、本格的に出てくるようになる前に対策をする必要があるのです。
また、霜降の時期には太平洋側から強い風が吹き始めますので、この強い太平洋側からくる一番の風を「木枯らし一号」と呼んでいます。
それ以外にそこまで大々的に行われるイベントや風習はありませんので、特筆すべきことが少ないシーズンでもあります。
最近はやりのイベントとしては10月31日に行われるハロウィンがありますが、本来なら近所の家々を回ってお菓子をもらうというちょっとした習慣であり、古代ケルト民族の先祖の霊を迎える儀式だったのですが、日本だとコスプレをして大きな騒ぎをするイベントとなってしまっているので特殊な進化をしている状況と言えるでしょう。
ちなみに、なぜここまでハロウィンが大々的なイベントになったのかを考察している人はいろいろといますが、最もしっくり来たのは「インスタ映えのために目立ちたいという人が劇的に増えた」ということと「クリスマスに高い金を払ってデートをする人が激減して、その分だけハロウィンに流れた」という二つの考えです。
現代日本人はなんだかんだで叫んで遊んで発散する場所が好きな人は多く、そのように発散する場所としてハロウィンを有効活用しているとよく言われております。
クリスマスだとパートナーがいない人は全く盛り上がれないのですが、ハロウィンは何の問題もなく個々人で盛り上がれますので良いタイミングなのでしょう。
実際にクリスマスのイベントが縮小しつつある中、ハロウィンのイベントはますます盛況になっております。
今年もハロウィンはより多くの人が集まることが予想されており、大混雑も予想されています。
次の節気である立冬まで行くと七五三や酉の市、ボジョレヌーボー解禁や新嘗祭といったイベントがあります。
霜降の季節の花は何?

10月下旬と11月上旬にまたがっている霜降の花で代表的なものはコスモス・山茶花・シクラメン・ジャスミン・カンツバキ・マリーゴールド・バンジー・ベゴニア・ランタナあたりでしょう。
特に、シクラメンは11月の誕生花となっておりますので、代表的な花の一つとして覚えておくといいでしょう。
霜降以外の二十四節気を紹介!

霜降の意味や由来などについて解説してきましたが、二十四節気はあと23個もあることを知っていますか?
ここでは霜降以外の二十四節気についてまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
二十四節気を理解することで日々の生活に役立てることができますよ。
立春
雨水
啓蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小満
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
処暑
白露
秋分
寒露
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
霜降に関するよくある質問まとめ
「霜降」とは、具体的にどのような意味を持つのでしょうか?
「霜降」とは、二十四節気の一つであり、この時期になると初めて霜が降りることが多くなることからこの名がついています。
また、これを境に本格的な寒さが訪れることを示す節気としても知られています。
何月頃に「霜降」は訪れるのでしょうか?
「霜降」は毎年、10月23日ごろを指すことが一般的です。
ただし、気象条件や地域の違いによって、霜が降りる日付は異なる場合があります。
「霜降」の時期に特有の食材や旬のものは何ですか?
「霜降」の時期は、さつまいもや栗、リンゴなどが旬を迎えます。
また、魚介では鰆や秋刀魚が美味しい時期となるため、これらの食材を楽しむことができます。
「霜降」の時期に気を付けるべき健康上のポイントはありますか?
「霜降」の時期は、朝夕の冷え込みが強まるため、温度差による体調不良を防ぐための注意が必要です。
特に、冷え性の方や高齢者は、暖房器具の使用や温かい服装での体温管理を心掛けると良いでしょう。
「霜降」はどのような行事や風習と関連していますか?
「霜降」自体に特定の行事や風習があるわけではありませんが、この時期は稲刈りの終わりや新米の収穫が行われる地域が多いです。
そのため、新米を使った食事を楽しむ文化や、収穫を祝う地域の祭りがこの時期に行われることが一般的です。
「霜降」の後に訪れる二十四節気は何ですか?
「霜降」の後に訪れるのは「立冬」です。
これは冬の始まりを意味する節気で、11月7日ごろに訪れることが一般的です。
「立冬」を境に、一段と冷え込みが増してきます。
「霜降」の時期の気象変動に関連する留意点はありますか?
「霜降」の時期は、急な寒気の流入や気温の大きな変動が見られることが多いです。
また、霜や初雪が降る地域も増えるため、農作物への影響や、滑りやすい路面などの交通安全への注意が必要となります。
「霜降」という言葉の由来や歴史にはどのような背景があるのでしょうか?
「霜降」という言葉は、文字通り「霜が降る」ことから名付けられました。
古くからの農業国である日本では、霜の降るこの時期が稲の収穫を終え、次の作物の準備をする大切な時期とされていました。
「霜降」の時期におすすめのレジャーやアクティビティは何ですか?
「霜降」の時期は、紅葉が始まり、多くの場所で美しい景色を楽しむことができます。
紅葉狩りやハイキング、キャンプなどのアウトドア活動がおすすめです。
また、新米の収穫時期と重なるため、新米を楽しむ農家体験なども人気です。
「霜降」に関することわざや詠み言葉、俳句にはどのようなものがありますか?
「霜降」に関連する言葉や詠み言葉は多数ありますが、代表的なものとしては、「霜降りて秋深し」という句があります。
この句は、霜が降ることで一層秋の深まりを感じることができる、という意味合いを持っています。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は霜降についての情報をまとめてまいりました。
ハロウィンというイベントがある季節なので、覚えやすい節気と言えるでしょう。
今では1年で最もお金をかけるシーズンとなっている人も増えていますので、見ている側もとっても楽しい時期となっています。
ただし、騒ぐ側の人たちは迷惑にならないようにだけ注意しつつ行動しましょう。



コメント