入梅(にゅうばい)という表現は、日本の季節の節目を指す言葉で、とりわけ梅雨の始まりを告げる時期を意味します。
ただし、現代の日本人の生活においてはこの言葉に馴染みがないという人も少なくないかもしれません。
本稿では、このやや見慣れない「入梅」という語句の読み方とその背後にある概念を、易しく解きほぐしていきます。
由来や意味合いについても掘り下げ、漢字「梅」が示す季節感とどのように関連しているのかを解明していきます。
「入梅」という語彙を知ることで、梅雨という季節を迎える際の日本特有の文化や表現に対する理解が深まり、言葉の持つ豊かな意味を感じ取ることができるでしょう。
入梅の意味や由来について

入梅は季節の移り変わりを理解しやすくするために設けられた雑節の一つであり、「梅雨入り」の漢語表現となっています。
ちなみに梅雨が終わるという意味を持つ言葉で出梅というものも存在していますが、今ではほとんど使われていません。
昔は今みたいに衛星も無ければ正確な梅雨入りをキャッチすることは不可能だったので、雑節の一つである入梅の期間が梅雨の期間と言えたでしょう。
しかし、今では梅雨入り宣言と梅雨明け宣言が気象庁などを含めた様々なところから出されますので、梅雨入りと梅雨明けは100%これらの発表に頼ります。
由来は梅雨に入ったという意味になりますので、梅雨という言葉が誕生したことと大きく関わっています。
最も信憑性が高い説は中国ではカビの生えやすい時期ということで梅雨は「黴雨(ばいう)」と表現されていたが、カビではあまりにも表現的によろしくないということで同じ「ばい」という読み方ができる「梅」に置き換わったという説です。
そこから梅雨の時期を表現することに「梅」を使うようになり、梅雨に入ることを入梅、梅雨から出ることを出梅と言うようになったと考えることができます。
入梅の正しい読み方

入梅とは秋分や春分といった二十四節気の暦日や端午の節句といった五節句などの暦日以外に、季節の移り変わりをよりつかみやすくするために設定された日本独自の暦日の一つです。
ちなみに、雑節には節分・彼岸・社日・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日・二百二十日とありますが、その中でも有名なのが節分や彼岸や八十八夜でしょう。
それらと比べると入梅は知名度的にかなり落ちてしまいます。
この入梅の読み方は「にゅうばい」となっていますが、「ついり」や場合によっては「つゆいり」とも読むことができるので覚えておきましょう。
この読み方でわかるように、この入梅の意味は梅雨に入ったことを意味する雑節となっております。
入梅はいつからいつまでのこと?
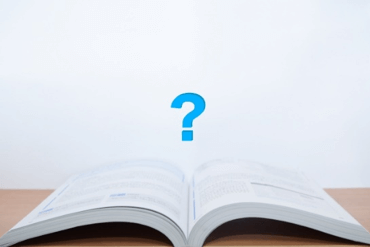
入梅とは梅雨入りしている期間なので、梅雨入りシーズンはいつなのかと考えると住んでいる場所によって大きく異なるのではっきりと言えなくなってしまいます。
ただし、通常の梅雨の期間と入梅では考え方が異なるので期間も多少異なってくるのです。
一応入梅のタイミングは太陽黄径が80度になるタイミングと決まっているので、2020年ならば6月10日となりますが、そこから約30日間が入梅となるのです。
つまり2024年なら6月10日からだいたい6月30日までが入梅となってきます。
昔は二十四節季の一つである芒種の後の最初の壬が入梅でしたが、今では太陽の位置を優先する太陽黄径の角度を重用しているのでその考えかたはしなくなりました。
実際の入梅と梅雨入りのタイミングは大きく異なることがありますので、あくまでも季節感をつかむために設定されたのが雑節の一つが入梅と考えてください。
東北にいても関東にいても九州にいても入梅は一緒ですが、梅雨入りは住んでいる地域が違うなら違うのです。
「入梅」と「梅雨入り」の違いは?
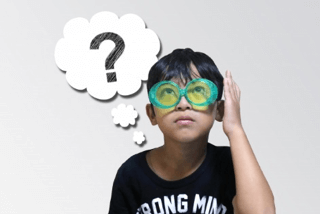
入梅は雑節として時期が決められていますが、梅雨入りはあくまでもそのときの気象や環境に合わせて変動していくというのが大きな違いでしょう。
太陽の黄径が80度に達する日から約30日が梅雨の期間と考えられていましたが、冬至は今のように気象予報を得ることができなかったのでこのように考えるしか無かったのです。
それでも、その年の気候や気象は作物の取れ高に大きく影響を及ぼすので梅雨のタイミングがいつなのかを漠然とでも知ることは非常に重要でした。
今ではこの入梅にはまったく頼っていないので、あくまでも昔の暦を知るために定められていた雑節の一つという認識になっています。
ちょっとした季節を表すための言葉としても使われますので、雑節の一つだったということを覚えておけば問題ありません。
現代人でこの雑節による梅雨入りの判断と気象庁による梅雨入りの判断どちらを選ぶのかと問いかければほぼ100%の確率で後者を選ぶでしょう。
「入梅の候」の正しい使い方

入梅の使い方として今でも最も多いのが梅雨入りの表現として用いるケースです。
その筆頭が「入梅の候」といった時候の挨拶でしょう。
二十四節季や雑節はこのように「○○の候」といった時候の挨拶として用いることができるので、社会人となって挨拶の文章を色々と作らないと行けない状況になったときに、二十四節季や雑節を覚えていると役立つのはこのような場面なのです。
この「入梅の候」とは「にゅうばいのこう」と読み6月上旬の期間だけ使える、「梅雨入りの季節になりました」という意味を持った挨拶となります。
この「○○の候」における「候」には自然現象や季節や気候という意味がありますので、二十四節季や雑節とセットで季節を表す時候の挨拶として用いられるのです。
具体的には「入梅の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」といった使い方をしますが、実際に梅雨入りしていない場合は使い方が異なってきますので気をつけてください。
梅雨入れしていなかった場合はちょっと文章に工夫が必要になってしまいますので、時候の挨拶になれていない方は無理に使わない方が良いでしょう。
具体的な使い方の例として「入梅の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」を紹介しましたが、それ以外にも「入梅の候、はっきりとしない天気が続いておりますがいかがお過ごしでしょうか」とか「入梅の候、○○様におかれましてはご活躍のこととお喜び申し上げます」といった使い方ができます。
ここら辺の使い方はいわゆるテンプレート化しているので、そこからコピーしてミックスすればそれらしき形になるでしょう。
ただし、梅雨入りしていないのにこの入梅を使う場合は「入梅とはいうものの、天候に恵まれ空梅雨になりそうですがいかがお過ごしでしょうか」といった別の使い方をしてください。
「入梅の候」はいつからいつまで使うのが正しい?

この「入梅の候」とは「にゅうばいのこう」と読み6月上旬からだいたい中旬の期間だけ使える、「梅雨入りの季節になりました」という意味を持った挨拶となります。
時期がずれた場合は夏至や小暑といった二十四節季や「初夏の候」や「梅雨の候」といった言葉を使うと良いでしょう。
使うタイミングが良くつかめないという人は使うタイミングがはっきりしている二十四節季を時候の挨拶に使うのが最も簡単となっております。
「入梅いわし」とはなに?

入梅鰯(にゅうばいいわし)は梅雨の真鰯のことをいいます。
この梅雨の時期の真鰯は一番脂がのっておいしいとされていて、刺身や煮付け、天ぷらなどにすると美味しく食べることができます。
しかし、真鰯は駄目になりやすい魚ですので、鮮度の良いものを選んで購入するようにしてください。
入梅鰯を食べるイベントが千葉県銚子市で開催されています。
毎年6月から7月末まで「銚子 うめぇもん入梅いわし祭」が開催されていて、鰯の御膳などを堪能することができます。
梅雨の時期で外に出る気が出ないかもしれませんが、ぜひ脂の乗った入梅鰯を堪能してみてはいかがでしょうか?
入梅に関するよくある質問まとめ
入梅とはどのような期間を指すのですか?
入梅は、日本における梅雨の始まりを意味し、一般的には6月初旬から中旬にかけてとされています。
この期間は地域によって多少の前後はありますが、日本列島が南から北へと梅雨前線の影響を受け始め、じめじめとした雨の多い時期に入ることを表します。
入梅の具体的な日付は気象庁が発表するため、毎年の公式な日付はその発表を待つ必要があります。
入梅の期間、農業ではどのような対策が取られるのでしょうか?
入梅の期間中は、農業において特にカビや害虫の発生に注意が必要です。
湿気が高いため、作物の病気が発生しやすく、特に水はけの悪い土地では根腐れのリスクも高まります。
そのため、適切な排水対策や、防虫・防カビ対策を事前に施すことが大切です。
また、雨が続くと作業ができない日も多くなるため、天候に左右されない作業計画を立てることも重要です。
入梅にちなんだ行事や風習は存在するのですか?
入梅に関連した特定の全国的な行事や風習はあまり知られていませんが、地域によっては梅雨入りを告げる伝統的な神事を行うところもあります。
また、家庭では梅雨を乗り切るための準備として、湿気対策としての除湿剤の使用や、カビ防止対策などが行われます。
梅雨の時期にあたるこの入梅には、室内干しのための洗濯物乾燥機や、湿気取りグッズが売れる時期でもあります。
入梅の時期に旅行を計画する場合、どのような点に気をつけるべきですか?
入梅の時期に旅行を計画する場合は、雨による影響を考慮する必要があります。
屋外アクティビティは雨天中止となることもあるので、屋内で楽しめるプランを立てるか、雨でも楽しめるアクティビティを選ぶと良いでしょう。
また、交通機関にも影響が出ることがあるため、時間に余裕を持って移動する、防水加工された荷物の準備をするなど、梅雨特有の天候に対応した計画が求められます。
入梅の季節におすすめの食べ物やレシピはありますか?
入梅の季節は湿気が多く体感温度が高くなるため、体を冷やしすぎないように注意しながらも、さっぱりとした食事がおすすめです。
たとえば、ショウガを使った料理は身体を温める効果があり、梅雨のじめじめとした気候に対抗するのに適しています。
また、梅を使った梅シロップや梅ジュース、梅干しは消化を助け、疲労回復にも効果的です。
湿気対策として塩分を適度に取り入れることも大切で、塩分とミネラルを含んだ食品を摂ることを心がけましょう。
入梅に適した室内の湿度はどの範囲で保つべきですか?
入梅の時期の室内では、適切な湿度の維持が快適さを保つ上で重要です。
理想的な室内湿度は、一般的に50~60%とされています。
これはカビの発生を抑えつつ、快適な生活環境を保つための範囲です。
湿度が高くなりがちなこの季節には、除湿機やエアコンの除湿機能の使用、通気を良くすることで室内の湿度を適切なレベルに保つ工夫が求められます。
入梅期に増える害虫対策はどのように行うべきですか?
入梅期には、湿度の高さからゴキブリやダニといった害虫が発生しやすくなります。
これらの害虫対策としては、家の清掃を徹底し、食べ物の残りかすを放置しない、ゴミをこまめに出す、排水溝を清潔に保つといった基本的な衛生管理が有効です。
また、市販の害虫防止剤を適切な場所に配置することも効果的です。
梅雨のジメジメを解消するためのおすすめのアロマオイルはありますか?
梅雨の時期のジメジメ感を解消するためには、リフレッシュ効果のあるアロマオイルがおすすめです。
例えば、ペパーミント、ユーカリ、レモングラスなどの爽やかな香りは、湿気による不快感を軽減すると同時に、リラックス効果も期待できます。
これらのアロマオイルをディフューザーで室内に拡散させることで、心地よい空間を作り出すことができます。
入梅中の洗濯物が乾かない時の対策は?
入梅中は屋外での洗濯物の乾燥が困難になることが多いです。
そんな時には、室内での干し方に工夫が必要です。洗濯物はなるべく広げて風通しを良くし、扇風機や除湿機を利用して空気を循環させることが効果的です。
また、部屋干し専用の洗剤を使う、消臭・抗菌スプレーを活用することも臭い対策になります。
天気の良い日を見計らってまとめて洗濯するのも一つの方法です。
入梅期に気をつけるべき健康管理はありますか?
梅雨の時期は気圧の変動が激しく、体調を崩しやすい時期でもあります。
特に気をつけたいのは、湿度の高さによるカビやダニなどのアレルゲンが原因のアレルギー反応です。
除湿と換気を心がけ、清潔な環境を保つことが重要です。
また、ジメジメとした天気による気分の落ち込みを防ぐためには、室内での適度な運動やバランスの良い食事、十分な睡眠が推奨されます。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は入梅について詳しく解説しました。
入梅は梅雨入りを示す雑節だったのですが、今では時候の挨拶や季節を表す表現の一つとしてしか用いられないので、今の日本人的にはかなり馴染みの薄い雑節となってしまいました。
しかし、時候の挨拶で登場することもありますので、相手方がこのような表現をしてきたら直ぐに意味をくみ取れるようになりましょう。


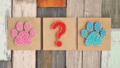
コメント