季節を表すものの中でも歴史がかなり古く今でもその名残が多く残っているのが二十四節気であり、小寒もその中の一つです。
今回はこの小寒は、いつなのか、意味や由来はどうなっているのか、小寒のことわざや小寒の候という言葉の意味、その時期の旬な食べ物について解説いたします。
夏至や冬至と比べて覚えにくい小寒でもコツをつかめばすぐに覚えられるようになるでしょう。
小寒の意味や由来は?
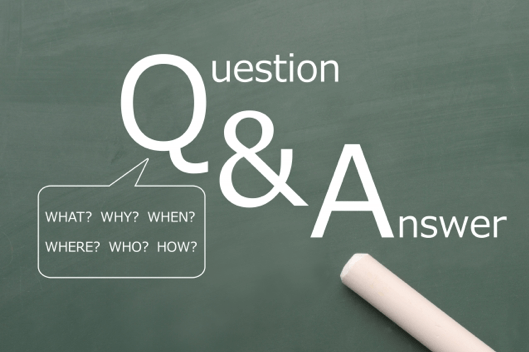
小寒という字を見ると「小さな寒さがくる」というイメージを持たれてしまいますが、二十四節気における「寒」という字は「最も寒い時期」に該当します。
つまり、小寒とは「最も寒い時期が始まる季節」となるのです。
日本語でも「寒の入り」という言葉がありますが、この寒の入りがまさに小寒が始まったタイミングとなります。
また、「寒の開け」と呼ばれるタイミングが立春の前日で、この寒の入りから開けまでの間を「寒の内」という表現をします。
由来もそのままで、この二十四節気という考え方が誕生した中国中原にある大都市洛陽でも1月が最も冷え込むためにこのような名前になったのです。
ちなみに、二十四節気を江戸時代の人たちが解説している暦便覧では、小寒は「冬至より一陽起るが故に陰気に逆らう故益々冷る也」と記載してあります。
つまり、「寒さが本番になり池や川の氷も厚みをますタイミング」と紹介しているのです。
江戸時代の日本でも1月はかなりの寒さになっていたのでしょう。
また、二十四節気を3分割してより細かい表現で表したものに七十二候というものがあるのですが、こちらを日本向けにアレンジしたものもありますので、そちらも確認しておきましょう。
この七十二候は初候・次候・末候の3つに分けられますが、それぞれ芹乃栄(せり すなわち さかう)、水泉動(すいせん うごく)、雉始雊(きじ はじめて なく)という表現がされています。
つまり、小寒とは「芹がよく生育して、地中で凍った泉が動き始め、雄の雉が鳴き始める季節」と表現しているのです。
2023年の小寒はいつ?

2023年の小寒は1月6日から1月19日までなので、お正月が終わったら小寒になると考えるとわかりやすいでしょう。
小寒は冬を表す二十四節気の一つで、「立冬⇒小雪⇒大雪⇒冬至⇒小寒⇒大寒」という並びになっています。
つまり、冬至の次の節気に該当するのです。
一つの節気は約15日となっています。
冬至や夏至がいつになるのかはかなり覚えやすいので、そこからだいたい15日経過した日から小寒がスタートすると考えるとイメージがしやすくなるでしょう。
小寒の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?

小寒の候とは時候の挨拶の一つで、「小寒の時期でございます」といった丁寧なあいさつとなります。
使えるタイミングは二十四節気における小寒のタイミングなので、ずれないように注意しましょう。
ダイレクトで送信できるメールならば二十四節気のタイミングを間違えない限り時候の挨拶を間違えることはないでしょうが、手紙といった到着するまでにタイムラグがあるものに記載するときには注意が必要です。
二十四節気がちょうど切り替わるタイミングでは時候の挨拶として二十四節気は使わないほうが安心でしょう。
小寒に食べる食べ物は?

お正月が終わったタイミングでやってくる小寒に食べる食べ物は何があるのでしょうか。
最も日本人的になじみがあるのはせり・なずな・ははこぐさ・はこべ・ほとけのざ・すずな・すずしろといった春の七草を入れた「七草がゆ」を食べることでしょう。
ただし、関東地方ではお正月が終わる1月7日までを「松の内」と表現し、その7日に七草がゆを食べるのですが、関西地方では15日までが「松の内」なので七草がゆも15日に食べるという人が多いです。
また、お正月飾りの一つである「鏡餅」も11日にある鏡開きで割って食べるという風習もいまだに残っています。
1月15日は小正月として小豆粥を食べる風習もあったのですが、今ではそれよりも成人式のほうが注目を集めておりこの風習はかなり薄れてしまったといわれております。
正月はこのようにいろいろと食べるものがありますので、はっきり言って太ります。
正月中はお餅を食べるという人もいるでしょうが、余ってしまったお餅がもったいないということで小寒になっても食べ続ける人もいるでしょう。
お餅ははっきり言って高カロリー高糖質の食べ物なので、がっつりと食べ続けると体重もガツンと増えてしまいます。
タラやヒラメや胃イセエビやタラバガニといった海産物も旬な時期ですし、レンコンやブロッコリーやホウレン草といった野菜も旬の時期なので、おいしいものには困らない時期でもあります。
「小寒の氷大寒に解く」のことわざの意味を教えて!

小寒を使ったことわざに「小寒の氷大寒に解く」というものがあります。
このことわざの意味は解説されている方々の言葉をそのまま持ってくると「物事が必ずしも順序通りにいかないことのたとえ」となっています。
要するに、本来ならば大寒のほうが寒くなるはずなのに小寒のほうが圧倒的に寒かったという意味です。
今の世界の気候はエルニーニョなどで暖冬異変が発生することも多く、今まで寒かった時期が温かかったり、急激に寒さが戻ってきたりといった異常気象がしばしば発生します。
つまり、今まで当たり前のような季節の移り変わりや温度の推移が当てはまらないということです。
このことわざの意味を聞くと現代日本の方々は納得しやすいのではないでしょうか。
小寒の時期にある風習は?

小寒のタイミングで発生する有名な風習は、先ほど紹介した健康祈願で七草がゆを食べるというものと、鏡開きと小正月と成人式でしょう。
成人式はもともと1月15日に固定されていたのですが、ハッピーマンデー制度が施行された2000年から1月第2月曜日に変わりました。
これらのタイミングで何らかのイベントが行われることも多いので、正月が終わってもまだまだやることはいろいろとある季節といえるでしょう。
小寒の季節の花は何?

1月中旬に該当する小寒の花といえばいくつかありますが、その中でも代表的な花は梅・シクラメン・ツバキ・パンジー・ポインセチア・カーネーション・フクジュソウ・マーガレット・クリスマスローズ・バラなどが該当します。
クリスマスローズやパンジーなどはガーデニングでも人気の花なので、周りにガーデニングが趣味の人がいれば高確率で見ることが可能です。
小寒以外の二十四節気はこちら!

小寒の意味や由来について詳しく解説してきましたが、小寒以外にもあと23個の二十四節気が存在しています。
様々な呼び方や意味や由来があって面白い内容になっているので、ぜひ小寒以外の二十四節気についてもチェックしてみてください!
それでは詳しくみていきましょう。
立春
雨水
啓蟄
春分
清明
穀雨
立夏
小満
芒種
夏至
小暑
大暑
立秋
処暑
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
大寒
小寒に関するよくある質問
「小寒」の意味や定義は何ですか?
「小寒」とは、二十四節気の一つで、この時期は冬の寒さが徐々に深まることを意味します。
名前の「小」は、次の節気である「大寒」よりもまだ寒さがそれほど厳しくないことを示しています。
どのような気象や自然の変化が「小寒」の時期に観察されるのでしょうか?
「小寒」の時期は、冷たい空気が日本全国に広がることが特徴的です。
多くの地域で最低気温が低下し、雪が降る場所も増えることが一般的です。
また、冬の果物や野菜が旬を迎え、新鮮な食材が市場に出回るようになります。
二十四節気の中で、「小寒」は何番目に位置していますか?
「小寒」は二十四節気の中で、23番目の節気として位置しています。
これに続き、次の節気は「大寒」となり、これが最後の節気となります。
「小寒」の時期に過ごしやすくするための対策やアドバイスはありますか?
「小寒」の時期は、冷え性の方や高齢者にとっては体調を崩しやすい季節となります。
したがって、暖房の使用や重ね着を心がけること、また、温かい飲み物や食事を摂取することで体を内側から温める工夫が大切です。
特に、しょうがやねぎを使った料理は、体を温める効果が期待されます。
「小寒」の時期に伝統的に行われる行事や食文化はありますか?
「小寒」の時期には特定の大きな行事は行われていないものの、冬の食材を楽しむ食文化が豊富にあります。
例えば、大根や白菜を使用した鍋料理や、寒ブリと呼ばれる冬の鰤を味わうなど、季節感を感じる食事が多く存在します。
「小寒」と「大寒」の違いは何ですか?
「小寒」と「大寒」は、両方とも冬の寒さを表す節気ですが、その名の通り「小寒」は寒さが始まる時期を指し、「大寒」は一年で最も寒い時期を指します。
したがって、「大寒」の方が「小寒」よりもさらに寒さが厳しくなることが特徴です。
「小寒」の日は毎年同じ日に設定されていますか?
「小寒」の日は、太陽の黄経が285度となる日を指します。
そのため、毎年1月5日または6日となりますが、僅かに日にちが変動することがあるため、毎年カレンダーで確認することをおすすめします。
この時期の「小寒」におすすめの過ごし方はありますか?
「小寒」の寒さを楽しむ方法として、温泉旅行やスキーやスノーボードといったウィンタースポーツを楽しむのがおすすめです。
また、家でのんびりとした時間を過ごす際は、こたつや電気毛布を使いながら冬の味覚を楽しむことも良いでしょう。
「小寒」の時期に特に注意したい健康上のポイントはありますか?
「小寒」の時期は乾燥が進み、風邪やインフルエンザの予防が特に重要となります。
手洗いやうがいをこまめに行い、加湿器を使用して室内の湿度を保つことがおすすめです。
また、外出時は防寒対策をしっかりと行い、体温の低下を避けるよう心掛けてください。
「小寒」をテーマにした詩や歌、言葉は存在しますか?
日本の古典文学や和歌には、節季や自然の変化を詠んだものが多く存在します。
「小寒」に直接言及した詩や歌は少ないものの、冬の寒さや風物を感じさせる詩や歌は数多く存在します。
例えば、古今和歌集や万葉集には、冬の情景や寒さを感じさせる和歌が収められています。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は小寒についていろいろと紹介してまいりました。
「小さい」という字が入ると日本人的には「大小」という意味でとらえてしまいがちですが、中国が発祥である二十四節気だと意味が異なることが多いのです。
「小」という字があっても「○○が始まるタイミング」と考えることができれば二十四節気も覚えやすくなるでしょう。
また、いつなのかを覚えるときは冬至や夏至といった日本人になじみがある節気を中心において考えるとやりやすくなります。

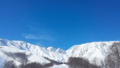

コメント