季節を表す用語である立春や夏至はなじみがありますが、啓蟄は読み方すらわからないのでいつなのか、風習や意味や由来も分からない人も多いでしょう。
そこで、今回はこの啓蟄とは何なのか、2024年はいつなのか、旬な食べ物や風習はあるのか、由来はどうなっているのかをお伝えいたします。
難しい言葉ではありますが、要点を抑えると簡単に理解できるようになります。
記事の最後には啓蟄以外の二十四節気についても紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
啓蟄の意味や由来、正しい読み方は?

二十四節気の1つである啓蟄の「啓」は「ひらく」という意味があり、「蟄」は「土の中にいる虫」という意味があります。
つまり、啓蟄とは「温かくなって土の中にいる虫が出てくる季節」という意味になるのです。
タイミング的にはまだ早いと感じる人もいるでしょうが、もともとこの言葉は中国の三国志よりも前の戦国時代である春秋時代に生まれたとされている言葉であり、その場所が紀元前の中国黄河流域の「周」があった国の洛陽を中心とする中原で考えられたといわれているのです。
この洛陽周辺の気候は3月が終わる頃から急激に温かくなって4月には20℃を超えて6月には30℃を超えるような気候となっています。
なので、3月中旬に当てはまるこの啓蟄は向こうの季節としては「虫が元気に出てくる季節」となるのです。
中国は梅雨もなければ台風による気候変動もないので、夏の時期がかなり長く温かくなるまでが早いのです。
寒くなるタイミングはほぼあっているのですが、この温かくなるタイミングは大幅にずれているので、春の節気にまつわる言葉は日本人には違和感が強くなってしまいます。
啓蟄の読み方は「けいちつ」で、時期は二十四節気でいうところの太陽の位置を表す黄経が345度になっている期間です。
2024年の啓蟄はいつ?

2024年の場合は3月5日からとなりますので、覚えておきましょう。
ちょうどひな祭りが終わったころに始まり春分の日で終わりますので、比較的覚えるのは簡単です。
二十四節気の区切り方では一つの季節を大体15日としています。
春を表す節気は「立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨」の6つなので3番目に来るのが啓蟄となります。
あまり聞き覚えのない二十四節気でも、立春や春分といった有名なものと絡めれば覚えやすいでしょう。
啓蟄の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?

手紙やメールでの正式な挨拶には「時候の挨拶」を用いることになります。
その中の一つが「啓蟄の候」という言葉です。
時候の挨拶として用いられることが多いこの「候」ですが、これは「~の季節」とか「~の天候」という意味があるので、「啓蟄の候」と記載したら「早春の季節」とか「虫が出てくるようになった天候」という意味になるのです。
時候の挨拶としてこのように二十四節気を使う場合は、そもそもの二十四節気がどのように区分けされているのかを覚えれば自然とタイミングもわかるようになっています。
啓蟄に食べる食べ物は?

立春といった季節の変わり目は邪気が大量発生する季節ということで、邪気を払う何かを食べるという風習がありますが、啓蟄ではそのような習慣はあまり存在していませんので旬の食べ物を食べることを意識するだけでいいでしょう。
3月が旬なものは野菜で考えると明日葉・ウド・かぶ・からし菜・カリフラワー・キャベツ・水な・シイタケ・クレソン・春菊・セリ・セロリ・玉ねぎ・にら・パセリ・ブロッコリー・分葱・ワラビあたりでしょう。
果物なら甘夏・オレンジ・キウイ・デコポン・八朔・マンゴーあたりが該当します。
魚を含めた海産物だと、赤貝・アサリ・イイダコ・ヤリイカ・牡蠣・数の子・サヨリ・鰆・白魚・しらす・鯛・ハマグリ・ヒジキ・ほうぼう・ワカサギ・わかめなどが該当します。
このようにいろんな食べ物が旬になっていますので、これらの食べ物を選んで食べるだけでも満足できるでしょう。
啓蟄の時期にある風習は?

啓蟄の日に行われる風習として最も有名なのがひな人形を片付けることでしょう。
ひな人形を飾るというのはもともと啓蟄の前の二十四節気にあたる雨水のタイミングなので、啓蟄に切り替わったらすぐに片付ける必要があるのです。
片付けるのを送れるとそのまま根気が遅れるというお話もありますし、3月の中旬に遅れたとしても晴れている日にしまったほうがいいというお話もあるので、この部分のお話はいろいろと錯綜しているといえるでしょう。
他には多少マイナーとなりますが、菰外し(こもはずし)と呼ばれる行事も存在します。
これはマツカレハという害虫から草木を守るために藁を巻く「菰巻き(こもまき)」を外すイベントなのですが、どうも本当に害虫駆除の効果があるのかは怪しいようで冬の風物詩という扱いになっているようです。
また、外した菰はその後に菰焼きというイベントで燃やすことになるようです。
3月16日に行われるイベントに十六団子と呼ばれるものがあり、こちらは豊作を願うために田んぼの神様にこのお団子をお供えするという農家の方々に伝わる伝統行事となっております。
具体的な神様の形があるわけではないので、銅像や絵姿はほとんどないといわれております。
また、16個の団子を作るために臼と杵を使って餅つきをする音で山から田んぼに降りてくるといわれている不思議な神様なのです。
ただし、日本各地に信仰のある神様であり、地方独自の様々な呼び方があるようで、統一性がありません。
今でもこの風習が根強く残っているのは東北地方と北陸地方といった農耕地帯なのでその時期に赴けばこの風習を目の当たりにできる可能性も高いです。
啓蟄の季節の花は何?

啓蟄は2024年なら3月5日からとなっているので、この時期の誕生花が季節の花として当てはまります。
3月の誕生花がチューリップなので、啓蟄の季節を表す花としてはうまくマッチするでしょう。
それ以外には、ヤグルマギク・土筆・ニリンソウ・ニゲラ・アセビ・ルピナス・ハナビソウ・アネモネ・イカリソウ・アーモンド・ドクゼリモドキ・クチナシ・サンシュユ・ハナミズキ・コエビソウなどがこの啓蟄を代表する花と言えそうです。
啓蟄に関するよくある質問まとめ
「啓蟄」とは具体的にどのような意味を持つのでしょうか?
「啓蟄」は、春の節気の一つであり、文字通りの意味は「虫が土から出てくる」という意味を持っています。
この時期になると、冬の間に地中で休眠していた虫たちが活動を始めることを示唆しています。
「啓蟄」の時期に特有な気象や自然の変化はどのようなものがありますか?
「啓蟄」の時期は、春の暖かさが増し、冬の寒さから徐々に解放される時期です。
雪が溶け始め、木々や草花が芽吹き始めることも多く、春の訪れを実感する時期となります。
「啓蟄」の節気には、どのような行事や風習があるのでしょうか?
「啓蟄」には、春の訪れを祝う行事や風習が多く存在します。
例としては、梅の花見や、新しい季節を迎える準備としての大掃除、また種まきの開始など、新たな生活のスタートを切るための準備が行われます。
「啓蟄」の時期に旬となる食材や料理はありますか?
「啓蟄」の時期には、春の味覚が徐々に楽しめるようになります。
特に、春キャベツや新玉ねぎ、筍や菜の花など、新鮮で柔らかい野菜が市場に出回り始めます。
これらを使った春らしい料理が多くの家庭で楽しまれます。
「啓蟄」は他の国や地域でも認識されている節気なのでしょうか?
はい、「啓蟄」は日本だけでなく、中国や韓国などの東アジアの国々でも認識される節気の一つです。
各国で少しずつ意味合いや行事は異なることもありますが、春の訪れとともに自然の変化や生物の活動が活発になることは共通しています。
「啓蟄」は毎年同じ日に訪れるのでしょうか?
「啓蟄」は太陽の位置に基づいて決まるため、毎年同じ日に訪れるわけではありませんが、概ね3月5日から7日の間に訪れることが多いです。
具体的な日付は毎年の太陽の動きによって若干の変動があります。
「啓蟄」の時期はどのような服装が適していますか?
「啓蟄」の時期は春を迎える過渡期であり、日中は暖かくなることが多いですが、朝晩はまだ冷え込むことも。
そのため、レイヤードスタイルやカーディガン、ライトアウターを活用して、調節できる服装がおすすめです。
「啓蟄」に関連する言い伝えや風習は他にも存在するのでしょうか?
「啓蟄」には「蟄虫啓戸」という言い伝えもあり、これは地中に隠れていた虫たちがこの時期に活動を始めることを意味しています。
また、昔からこの時期は雨が多く、それを示す「啓蟄の雨男」という言葉もあります。
「啓蟄」と同じく春を告げる二十四節気は他にどのようなものがあるのでしょうか?
春を告げる二十四節気には、「立春」「雨水」「啓蟄」「春分」「清明」「穀雨」の6つがあります。
それぞれが春の異なる側面や自然の変化を示しており、季節の移ろいを感じる手がかりとなっています。
「啓蟄」の後、次に訪れる節気は何でしょうか?
「啓蟄」の後に訪れる節気は「春分」です。
「春分」は昼と夜の長さがほぼ等しい日を指し、春の中盤を告げる重要な節気となっています。
春分の日は、多くの国々で休日となることもあり、春の到来を感じる特別な時期です。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は啓蟄についての気になる情報をひたすらまとめてまいりました。
啓蟄といった二十四節気は調べて仕組みがわかると日本の夏至や秋分なども簡単に理解できるようになりますので、ある程度の仕組みを覚えるといろいろとお得です。
ちょっとした豆知識としても披露できますので、是非ともこの情報をうまく活用して話題の中心になってください。
話のレパートリーが広がると社会人はいろいろと便利です。
啓蟄以外の二十四節気一覧はこちら!

今回はここまで啓蟄について詳しく解説してきましたが、他に23個もの二十四節気が存在します。
これを機に啓蟄以外の二十四節気についても見てみましょう。
知らなかったことをたくさん学べると思います。
二十四節気について一緒に理解を深めていきましょう。

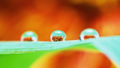

コメント