小満は季節を表す用語ではありますが、春分や夏至といったなじみがあるものではないので、具体的にいつなのか、旬な食べ物や由来、そしてその文字の意味するところが分かっている人は少ないでしょう。
そこで、今回はこの小満にまつわる様々な疑問を解説し、この時期特有の風習やイベントが存在しているのかも探っていきます。
小満の意味や由来は?
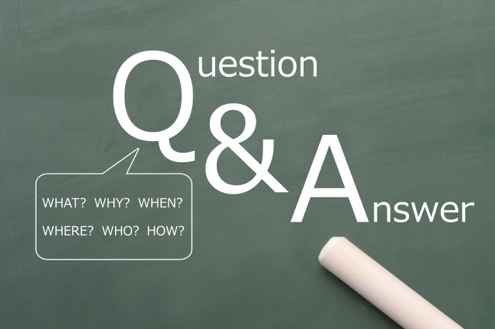
どことなく不思議なニュアンスがある小満ですが、この言葉の意味は「万物が次第に成長して一定の大きさに育つ」となっております。
いわゆる物事が満ちていく時期という意味を持っていますので、より作物が育っていくというイメージを持つとわかりやすいでしょう。
二十四節気をさらに約5日ずつの初候・次候・末候と3つに分けた七十二候を日本風に表現したものを紹介すると、初候が「蚕起食桑」、次候が「紅花栄」、末候が「麦秋至」となります。
わかりやすい言い方に切り替えると「蚕起食桑」は蚕が桑を盛んに食べ始めるようになって、「紅花栄」が紅花が大量に咲くようになり、「麦秋至」が麦が熟し麦秋となるとなります。
ただし、由来については諸説あるのでどれが正しいのかはわかりません。
昔は「少しの満足が可能な季節だから小満」という考え方がされていましたが、基本的に二十四節気は人間の感情を使ったものはないのでそれはあり得ないと否定する人が増えており、別の由来があるとされています。
最も有力なのが、「完全に実っている状態である大満までは到達していないけど、植物が実り始める時期なので小満と呼ばれるようになった」とか、「実はなっているけど成熟しておらずあと少しで満たされる状況にあるから小満と名付けられた」というものになります。
2024年の小満はいつ?

小満とは初夏を表す言葉であり、二十四節気では立夏に続く夏を表す用語となります。
時期としては国立天文台の発表を参考にすると、2024年の場合5月20日から6月4日までとなります。
ちなみに、二十四節気で夏を表す言葉は立夏⇒小満⇒芒種⇒夏至⇒小暑⇒大暑とつながりますので、特に覚えやすい立夏と夏至を起点として考えるとわかりやすいでしょう。
今回紹介する小満は立夏のあとで夏至の二つ前の季節となります。
小満の候の意味と正しい使い方は?

時候の挨拶にはこの二十四節気を使った挨拶が多々存在します。
その一つが「小満の候」という言葉で、「小満の候、貴社ますますご清祥のこと」といった使い方をするのです。
ただし、これらの二十四節気を使った挨拶というのはその季節にマッチしている期間だけ使えるので、小満という言葉を用いるのならば、小満の時期限定の言葉となるでしょう。
同じように時候の挨拶で二十四節気を使う場合は必ずその時期がどうなっているのかを確認してください。
先ほど紹介したときに参考にした国立天文台のページをブックマークしてチェックしておけるようにするとやりやすいです。
小満の時期はどんな季節感なの?

小満とは先ほどの言葉で出てきているように、「完全に実っている状態である大満までは到達していないけど植物が実り始める時期」であり、「実はなっているけど成熟しておらずあと少しで満たされる時期」となっています。
ただし、日本では温かくなってくる季節ではありますが梅雨が近づいて雨も増え始める時期ですので、気候の変動に気を付けなければいけないでしょう。
特に、学生さんの場合は6月1日に衣替えが始まる時期ですし、見た目を気にしている人たちにとっては大変な時期と言えるでしょう。
肌の露出度が確実に増えてきますので、それだけ自分の肌ケアが大変な時期になってきます。
少し話は戻って、二十四節気の七十二候でこの小満は初候が「蚕起食桑」、次候が「紅花栄」、末候が「麦秋至」と紹介しました。
ここで秋という単語が出てきてびっくりしている方もいるでしょうが、この秋というのは収穫期を意味する単語なので季節を表す言葉ではありません。
つまり、「麦秋」とは麦の収穫時期ということです。
二期作をしている農家では梅雨が本格的に始まる前に麦の刈り入れを行うのでかなり忙しくなってしまいます。
小満に行われるイベントや風習は?

小満で大々的に行われる伝統的なイベントというのはそう多くありません。
しかし、二期作における収穫期というのも相まって地方ではちょっとしたイベントが開催されることが多々あります。
その筆頭が長野県佐久市の稲荷神社で行われる「小満祭」で、300を超える露店やパレードやちょっとしたショーなど集客力が高いものが一通りそろっていることから注目度が高めとなっています。
ちなみに、二十四節気の小満は「しょうまん」と呼びますが、この祭りは「しょうまん」ではなく「こまん」と読むので注意してください。
群馬県甘楽群では標高1000mを超える場所にある神津牧場にて行われる、「神津牧場花まつり」という季節外れの春の花を堪能できるお祭りがあります。
一斉に咲くようにしっかりと調整しているので、ものすごく綺麗な景色を堪能できるでしょう。
さいたま市ではうなぎを使った「うなぎまつり」が開催されます。
非常においしいうなぎを大量に堪能できるので、うなぎが大好きな人たちが非常に集まるイベントとなっているのです。
小満の時期の旬な食べ物は?

小満の時期の食べ物と言えば秋麦なのですが、この秋麦を普段食べていない人にとっては使い方に悩んでしまうでしょう。
簡単な使い方はこれから夏に向けて必須となる麦茶として飲むのも非常に有効ですし、ご飯に混ぜて炊くという方法も存在します。
それ以外には、ソラマメ・ビワ・鱚あたりがこの時期旬を迎えますので堪能することができます。
それ以外に5月の下旬と6月の上旬が食べごろとなっているのは、アスパラガス・キャベツ・グリーンピース・クレソン・ジャガイモ・ゼンマイ・にんにく・ルッコラ・レタスといった野菜や、マンゴー・メロン・夏みかんといった果物です。
特に、この時期においしくなるメロンは濃厚なものがかなり増えますので果物好きな方は堪能してもらいたい一品です。
魚の場合鱚以外では、めばる・さわら・鰹・鯵あたりが旬な時期となってきます。
小満に関するよくある質問まとめ
「小満」とはどのような意味を持つ節気ですか?
「小満」とは、二十四節気の中のひとつで、毎年5月の中旬頃に訪れます。
名前の通り、「小さく満ちる」という意味合いがあり、この時期は穀物の種子が少しずつ実り始め、植物の成長が活発になることを示しています。
「小満」の時期の特徴的な気候や自然の変化は?
「小満」の時期は初夏の気配が濃厚になり、日中の気温が高くなる一方、朝晩はまだ涼しいことが特徴です。
また、新緑が鮮やかになり、多くの花が咲き誇る風景が広がります。
この頃から梅雨の入り口となり、ジメジメとした湿度が増してくる地域もあります。
「小満」の時期に行われる日本の伝統的な行事や風習はありますか?
「小満」の時期に特定の大きな行事や風習があるわけではありませんが、この頃から梅の実が成熟し始めるため、梅干しの仕込みや梅酒を作る家庭も増えます。
また、自然を楽しむピクニックやハイキングなどのアウトドア活動が盛んになる時期でもあります。
「小満」は他の国や地域でも認識されていますか?
「小満」は元々中国の二十四節気の一部として存在しており、日本だけでなく、韓国やベトナムなどの一部の東アジア諸国でも同様に認識されています。
ただし、その国や地域の気候や風土に応じて、少し意味合いや認識が異なることもあります。
「小満」の頃に注意すべき健康上のポイントはありますか?
「小満」の頃は気温が上昇し、日中は暑くなることが増えますが、まだ寒暖差が激しい日もあるため、体調を崩しやすい時期でもあります。
適切な服装や水分補給を心掛けること、また、湿度が高まる地域では、カビやダニ対策をしっかりと行うことが大切です。
「小満」の2024年の日付はいつですか?
二十四節気の「小満」は、毎年太陽の黄経が60度の位置に来たときに訪れるため、通常は5月20日~22日の間になります。
2024年の「小満」は具体的なカレンダーに従って判断することをおすすめします。
「小満」と「大満」の違いは何ですか?
「小満」という節気は実際に存在しますが、「大満」という節気は存在しません。
多くの人が「小寒」と「大寒」、または「小暑」と「大暑」のようなペアの節気を考える際に、「小満」にもペアがあるのではと誤解することがありますが、正確には「大満」は存在しません。
「小満」の時期に適した食材や料理はありますか?
「小満」の時期は初夏を迎える頃で、新鮮な旬の野菜や魚が多く市場に並びます。
特に、筍や新玉ねぎ、アスパラガスなどの春野菜や、鯵(あじ)、鰹(かつお)などの魚がおすすめです。
これらを使ったさっぱりとした料理や、季節の味を楽しめる和食が人気です。
「小満」に関連する言葉やことわざはありますか?
「小満」に直接関連することわざや成句は少ないですが、二十四節気全体に関連する言葉や、この時期の気候や自然を表す言葉、ことわざはいくつか存在します。
例えば、「早春賜物」や「春の七草」など、季節の移り変わりや自然を感じる言葉が多く使われます。
「小満」の頃におすすめの行楽地や観光スポットは?
「小満」の時期は新緑が美しいため、山や公園、庭園などの自然を満喫できる場所がおすすめです。
特に、日本の各地に点在する国立公園や、桜の名所として知られる場所は、この時期でも新緑や花々の美しさを楽しむことができます。
また、梅の花が咲き始める地域も多いので、梅の名所の訪問も良い選択です。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は小満について詳しく解説いたしました。
小満独自のイベントや風習というのは日本だと非常に少ないのですが、秋麦といった刈り入れ時期に合わせたイベントや風習は地方によっていろいろと残っていますので、休みがこの時期に固まった場合はちょっと遠出をすると楽しいイベントに遭遇できる可能性が高いです。
小満以外の二十四節気一覧を一挙紹介!

ここまで小満について詳しく解説してきましたが、他にも23個の二十四節気が存在します。
これを機に小満以外の二十四節気についても学んでみませんか?
二十四節気について学ぶことでその時の季節感や旬な食べ物や行事なども学ぶことができますよ。
ぜひ参考にしてみてください。



コメント