正月に飾るしめ縄は、日本の伝統的な装飾であり、新年を祝う大切な象徴です。
しかしながら、正しい飾り方や飾る期間については、多くの人が詳しく知らないことが多いです。
通常、しめ縄は新年を迎える少し前、大晦日に飾られます。
取り外す時期に関しては、地域や家庭によって異なりますが、一般的には1月7日か、小正月である1月15日までに取り外すことが多いです。
また、しめ縄を飾る位置や方向も重要で、縁起の良い方法で飾ることが望ましいです。
この記事では、そんなしめ縄の飾り方や期間、そしてその背景にある文化や意味について詳しく解説します。
しめ縄を適切に飾ることで、新年の喜びと祝福を心から感じることができるでしょう。
しめ縄の正しい飾り方や飾る場所は?

しめ縄を飾る際、まずはどこに飾ろうか悩みますよね。
それを決めるにはしめ縄の種類を把握しておく必要があります。
そもそもしめ縄とは一体どんなものなのでしょうか。
年末近くなるとスーパーなどでよく見かける飾りはとても華やかですよね。
あれはしめ縄に縁起の良い飾り物をつけた「しめ飾り」です。
本来のしめ縄とは神社などで見られるととてもシンプルなものになります。
わらを編み、神様の降臨を意味する「紙垂(かみしで)」をつけます。
一般家庭ではこのしめ縄を飾る方は少ないです。
しめ縄を家庭で飾る場合、「ごぼう注連(ごぼうじめ)」を使うことが多いです。
ごぼう注連はごぼうのように太いしめ縄のことです。
これは神棚向きのしめ縄で神棚につける時に紙垂を一緒に飾ります。
正月に飾るしめ縄は左にねじって作られる特別な「左綯い(ひだりない)」というものになります。
古来より左は神聖なものを意味していたため、神棚から見て太い部分が左側に来るように飾ります。
少しややこしいのですが、人間から見ると右側に太い部分がくるようになります。
また、玄関にしめ縄を飾ることもあります。
特に関西ではごぼう注連に「前垂れ」というわらの垂を一緒に飾る家庭が多いです。
ごぼう注連と前垂れに縁起の良い「裏白」「紙垂」「譲り葉」「橙」などを一緒に飾ります。
一方関東ではしめ縄を輪にした「玉飾り」を付けることが多いです。
これは太しめ縄を輪にし、縁起物を一緒に飾る飾り方です。
しめ縄はいつからいつまで飾る?

しめ縄の飾る場所と飾り方を理解いただいた上で、忘れてはいけないのがいつからいつまでの期間、飾るかということです。
これは飾り方や飾る場所と同じくらい重要なことになります。
しめ縄を飾る期間を日本では「松の内」といいます。
松の内とは門松を飾っている期間、つまり正月を意味します。
松の内は12月13日より始まります。
昔の人々が大掃除のルーツとした「すす払い」が12月13日だったため、その日から正月の準備をしてよい期間に入ります。
とはいえ、現在の日本ではクリスマスを祝う家庭が多いので、一般的にクリスマスが終了してから飾る家庭が多くなっています。
クリスマスをお祝いしない場合は、12月13日から飾り付けても問題ありません。
飾り付けを行う際、12月29日と30日、31日は飾るのを避けるようにしてください。
29日は「二重苦」を意味し、正月の飾りをつけるにはよくない日とされています。
また、旧暦の大晦日であった30日と現在の大晦日である31日は「一夜飾り」と呼ばれ、1日しか飾っていないもので神様を迎えるのは不適切とされています。
飾りを外すのは松の内が明ける1月7日、または1月15日です。
日が2パターンあるのは、地方差があるためです。
これは後程詳しくご説明しますね。
しめ縄を飾る意味と由来

そもそもなぜ日本ではしめ縄を飾るのでしょうか。
これは日本の神話に由来があります。
太陽の神である天照大神が弟の須佐之男命のいたずらに腹を立て、天の岩戸という場所に隠れてしまいます。
天照大神が隠れてしまうと太陽は現れません。
多くの神々がこれに慌て、踊りを踊り天照大神の気を引いて、天照大神を岩戸から出します。
そして再び岩戸に隠れられないよう、岩戸にしめ縄をつけ、結界を施したと言われていることから、しめ縄には結界を張る役割があります。
この結界を張ることが正月にはとても大切なことになります。
正月は年神様を迎え、一年の無病息災などを祈ります。
年神様に「ここは安全な場所ですよ」「不浄なものはありませんよ」と示すためにもしめ縄を飾り、年神様にふさわしい場所であることを示す必要があるのです。
しめ縄の正しい処分方法

では、正月が終わり、役目を果たしたしめ縄ですが、どう処分していいか悩みますよね。
処分の仕方がよくわからなくて一年前のしめ縄がそのまま家にあるという方も多いのではないしょうか。
しめ縄の処分方法として最も適しているのが神社などで行われる「どんど焼き」に出すことです。
どんど焼きは正月飾りを焼き、空に年神様を見送る行事です。
そのため、しめ縄を処分させていただくには最も適した方法になります。
ただし、どんど焼きはいつも行われているとは限りません。
一般的に1月15日に行われる場合が多いですが、その日に都合が悪かったり過ぎてしまっていた場合は神社で定期的に行われる「お焚き上げ」で処分させていただく方法もあります。
ただし、お焚き上げもいつ行われるかは神社によって異なるので、事前に問い合わせをしておくことが大切です。
神社によってはいつ持ち込んでも大丈夫なところもありますよ。
関東と関西で飾る期間が違う?

先ほど、しめ縄を飾る松の内は1月7日と1月15日までで地方によって異なるとご紹介しましたが、これは関東と関西で異なる場合が多いということです。
地方差はありますが、一般的に関東では松の内は1月7日まで、関西では1月15日までとされています。
なぜ地方差があるかというと、徳川家光が死去した日が大きく関わっています。
昔は松の内は全国共通で1月15日でした。
そして1月20日に鏡開きが行われていたのですが、徳川家光が4月20日に死去します。
この20日を鏡開きをするには忌日とし、1月11日に変更しました。
そのため、正月飾りも早く片付けたほうが良いと松の内の期間も1月7日までに変更しました。
このことがうまく関西には伝わらず、関西には古来からの1月15日までの風習が残っているとされています。
とはいえ、もし自分の住んでいる地域がどちらに当たるかよくわからないという場合は、1月7日に外しておけば問題はありません。
そして周りの家がいつ外しているかをチェックして、翌年地域の習慣に合わせてみると安心ですよ。
正月飾りに関するよくある質問
正月飾りとは具体的にどのようなものですか?
正月飾りは、日本の新年を祝うための伝統的な装飾品です。
これには門松(かどまつ)、しめ飾り、鏡餅(かがみもち)などが含まれます。
これらの飾りは、新年の幸運を招き、邪気を払うために家の入口や居間に設置されます。
それぞれが縁起の良い意味を持ち、新年の祝福と家族の安全を願う目的があります。
正月飾りはいつからいつまで飾るのが適切ですか?
正月飾りを飾る適切な時期は、一般的には12月の終わりから新年の初めまでです。
飾り始めは地域によって異なりますが、12月28日までに設置するのが一般的です。
飾り終わりは、小正月(1月15日)ごろまでとされていますが、地域や家庭によって異なる場合もあります。
正月飾りの主な種類とその意味は何ですか?
正月飾りの主な種類には、門松、しめ飾り、鏡餅があります。
門松は、神様を迎えるためのしるしとして玄関に設置され、家の繁栄と幸福を願います。
しめ飾りは、神聖な場所を示し、災いから家を守る役割があります。
鏡餅は、年神様への供物であり、家族の絆や豊かな収穫を象徴します。
自宅で正月飾りを手作りする際のポイントは何ですか?
自宅で正月飾りを手作りする際には、伝統的な意味を理解することが重要です。
門松は竹と松の枝を基本とし、しめ飾りはしめ縄と紙垂を用いて作ります。
材料の選定から組み立てまで、自分の家族に合わせたアレンジを加えることも可能です。
手作りすることで、その年の抱負や願いを込めることができます。
正月飾りの取り扱いや処分方法について教えてください。
正月飾りの取り扱いには、飾り期間が終わった後の処分方法が重要です。
伝統的には、どんど焼きなどで正月飾りを燃やし、神様に感謝を捧げる儀式が行われます。
これに参加できない場合は、自治体の指示に従って適切に処分することが推奨されます。
飾りを取り外す際には、壊れたり散らかったりしないように注意して取り扱いましょう。
正月飾りに用いる材料はどこで手に入れることができますか?
正月飾りに用いる材料は、日本国内のホームセンターや花屋、一部のスーパーマーケットで手に入れることができます。
特に、正月に向けて各店舗ではさまざまな種類の正月飾り用の材料を取り扱っています。
また、オンラインショップでも購入可能で、自宅で手作りするためのキットも販売されています。
正月飾りを飾る際に遵守すべき伝統的なルールはありますか?
正月飾りを飾る際には、いくつかの伝統的なルールがあります。
たとえば、門松は家の正面に向かって右側が高くなるように設置します。
また、しめ飾りは神聖な場所を示すため、清潔で目立つ場所に飾ることが望ましいです。
伝統的な意味を尊重し、適切な位置に飾ることが大切です。
正月飾りを長持ちさせるための保管方法は何ですか?
正月飾りを長持ちさせるためには、取り外した後に適切な保管方法が重要です。
天然素材で作られた飾りは乾燥を防ぐために、風通しの良い場所に保管すると良いでしょう。
湿度が高すぎるとカビが生える可能性があるため、適度な湿度の場所を選ぶことが重要です。
使用しない期間は、直射日光や埃が当たらないように保管してください。
正月飾りはどのような願いや祈りを込めて飾られますか?
正月飾りは、新年の幸運、家族の健康、事業の繁栄など、さまざまな願いや祈りを込めて飾られます。
これらの飾りは、新年を清らかな気持ちで迎え、災いを避けるための象徴とされています。
また、家族や地域の安全と幸福を願う意味合いもあり、年の始まりを祝う重要な役割を果たしています。
正月飾りの現代的なアレンジやトレンドにはどのようなものがありますか?
正月飾りの現代的なアレンジやトレンドには、シンプルでスタイリッシュなデザインが増えています。
伝統的な素材を用いつつも、モダンなインテリアに合わせやすい配色や形状が取り入れられています。
また、コンパクトサイズでスペースを取らない飾りや、洋風の要素を取り入れた飾りも人気です。
これにより、伝統的な正月飾りを現代の生活スタイルに合わせて楽しむことができます。
まとめ
しめ縄についてご紹介してきましたが、いかがでしたか?
しめ縄に結界の役割があること、日本の神話から由来されていることなど日本ならではの考え方があり、とても美しい行事ですよね。
今度の正月はぜひしめ縄を飾り、年神様に安心してきていただけるようにしてみてくださいね。

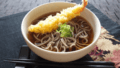

コメント