お雑煮は、日本の伝統的なお正月料理で、その地域によって異なるスタイルがあります。
特に、関東と関西でのお餅の形や味付けの違いは、日本の食文化の多様性を象徴しています。
関東では、角形のお餅を使い、醤油ベースで作られるのが一般的ですが、関西では丸いお餅と白味噌が特徴的です。
今回は、この関西スタイルのお雑煮のレシピ、その独自の特徴、由来、そして関東スタイルとの違いに焦点を当ててみましょう。
【関西のお雑煮】美味しくて失敗しないレシピ・作り方3選!

お雑煮のレシピは地方や地域だけでなく、各家庭によっても味付けが少し変わってくることも特徴の一つだと思います。
この記事では関西のお雑煮のレシピ中から三つピックアップしてご紹介します。
紹介するレシピを選んでいる時に気付いたのですが、関西のお雑煮は白味噌仕立てで丸餅が使われていて、その他の具材には大根、人参、里芋を使っているものがほとんどでした。
後はお好みで三つ葉や柚子の皮を乗せたりするものもありましたが、基本的には丸餅・大根・人参・里芋を使って作るようです。
ここで面白いのは使うお餅の種類や使う具材、白味噌仕立てであることは共通しているのに、レシピによっては調理方法が少し異なることです。
記事で紹介するレシピや参照動画を見比べ、その違いにも注目してみてください。
ちなみに関西のお雑煮が白味噌仕立てである理由は、お雑煮の発祥の地である京都で白味噌が作られていたことが理由と考えられます。
京都のお雑煮レシピ
今年は一味変わったお雑煮を作ってみよう!「 白みそ雑煮」の作り方 | お雑煮レシピ
材料(4人前)
大根…80g
金時人参…50g
八つ頭…120g
塩…ふたつまみ
昆布だし…800ml
白味噌…大さじ3と1/2
沸騰したお湯…適量
作り方
大根は厚く皮を剥き、5mm幅の輪切りにする。
金時人参も同じく厚く皮を剥いて5mm幅の輪切りにする。
八つ頭は芋同士を包丁で切り離して皮を厚めに剥き、乱切りにする。
乱切りにした八つ頭をボウルに入れてよく塩もみをしてから水で洗う。
鍋に昆布だし800mlを用意し、具材を入れて中火にかける。
沸騰する寸前で昆布を取り出し、灰汁が出てきたら取り除く。
八つ頭に火が通ったら火を止めて、白味噌を溶き入れる。
沸騰したお湯に丸餅を入れて茹でる。
お椀に丸餅と具材を先に入れてから汁をかけるように入れて出来上がり
料理の特徴
白味噌仕立てのお雑煮です。
こちらのレシピはお雑煮発祥の地とも言われている京都でのお雑煮のレシピだそうです。
使われている具材が里芋ではなく八つ頭なことも特徴と言えます。
ちなみに八つ頭とは里芋の一種で、親芋と子芋が分かれずに塊になっているそうです。
その見た目が頭が八つくっついて見えることから「八つ頭」と呼ばれています。
縁起物としておせち料理に使われている食材でもあります。
レシピについてですが、このレシピのポイントは八つ頭の調理だと個人的には思います。
動画内の説明によると八つ頭をよく塩もみしておくと、ぬめりが取れて味が染み込みやすくなるそうです。
里芋を使った関西風お雑煮のレシピ
【お正月の定番】やさしい甘みが広がる 白みそ 雑煮 のレシピ 作り方
調理時間:20分
材料(2人前)
大根…20g
金時人参…30g
里芋…2個
しいたけ…2枚
だし汁…500㏄
白味噌…80g
三つ葉…お好みで
作り方
下準備
大根と金時人参を5mm幅の薄切りにし、梅の花の形に飾り切りする。
里芋は皮を剥いて塩もみし、下茹でしてザルにあける。
しいたけは軸を取って飾り切りにする。
調理
鍋にだし汁500㏄入れ、飾り切りにした大根と金時人参を加えて具材が柔らかくなるまで中火で3分煮る。
具材が柔らかくなったら、里芋・しいたけ・丸餅を加え、時々かき混ぜながら丸餅が柔らかくなるまで中火で4分煮て灰汁を取る。
丸餅が柔らかくなったら弱火にして白味噌を溶き入れて、丸餅・具材からお椀に盛り付けて最後に汁をいれて出来上がり。
料理の特徴
こちらは里芋を使ったレシピになっています。
上の項でご紹介したレシピと同じ白味噌を使ったお雑煮ですが、調理する手順が少し違いますね。
丸餅を具材と一緒に煮込んでいます。
こちらのレシピでは具材を飾り切りにしているので、料理初心者にはそれだけで難易度が高く感じますが、飾り切りが出来たら仕上がりがお正月らしさを演出できそうです。
白味噌と合わせ味噌を使ったお雑煮のレシピ
『関西風お雑煮』ほっこりする白味噌ベース♪ / mogoo
材料(2人前)
大根…1/3本
人参…1/4本
里芋…1個
白味噌…60g
合わせ味噌…小さじ1
水…500ml
和風顆粒だし…小さじ1
かつお節…適量
作り方
里芋は皮を剥いて、5mm幅に切る。
大根は皮を剥いて5mm幅のいちょう切りにする。
人参は皮を剥かずにそのまま5mm幅のいちょう切り。
鍋に水と和風顆粒だしを入れ、具材を加えて5分ほど煮込む。
一旦火を止めて白味噌と合わせ味噌を溶き入れる。
再び火を点け、丸餅を入れて柔らかくなるまで煮る。
お椀に盛り付け、かつお節をまぶして出来上がり。
料理の特徴
白味噌と合わせ味噌を使ったお雑煮のレシピです。
こちらのレシピでは昆布だしではなく和風だしの顆粒タイプのものが使われていますね。
こちらのレシピでは丸餅を最後に煮込むようです。
最後にかつお節をまぶすのも特徴だと思います。
飾り切りはしないようなので、初心者でもトライできるのではないでしょうか。
関西のお雑煮の意味や由来
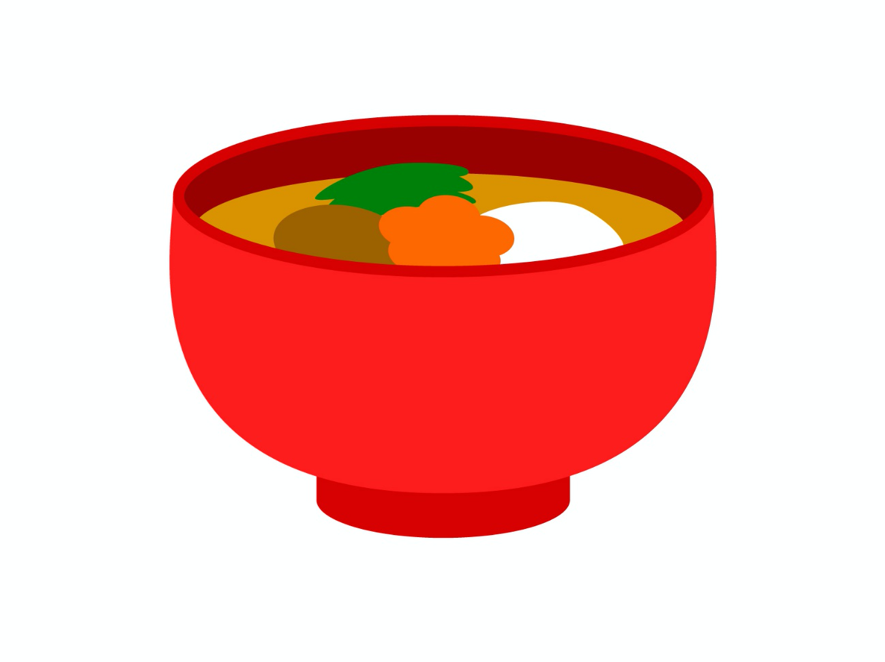
お雑煮の歴史は古く、室町時代に誕生した料理と言われています。
その発祥の地は京都で、元々は上級武士の婚礼で出されていたものだそうです。
その婚礼の儀で、新婚夫婦が三三九度の盃を交わす際に用意される酒の肴がお雑煮の起源とされています。
当時は丸餅にアワビやナマコなどの様々な具材を同じ鍋で煮た料理だったことから、「雑煮」という名が付けられたそうです。
お雑煮は宴の始めに食べられることから縁起がいい料理とされ、正月に食べるものへと変化していったようです。
そんなお雑煮の文化が庶民にも広まったのは江戸時代のことです。
それまでは公家や僧侶、裕福な商人の間でしか食されてなかったとされています。
また、お雑煮の文化が庶民に真っ先に広まったのは発祥の地である京都が最初でした。
婚礼の儀で出されていたお雑煮の具材には夫婦円満や豊作の意味が込められていたようです。
正月に食べられるようになってからは、お餅はよく伸びることから長生きできるようにという願いが込められるようになりました。
また、関西では「円満」を意味する縁起物として丸餅が現在でもお雑煮に使われているようです。
特徴や関東との違いは?
お雑煮は関西と関東ではどんな違いが?
関西のお雑煮の特徴は丸餅が使われていることと白味噌仕立てであることが挙げられます。
一方の関東では角餅が使われていて、醤油仕立てとなっています。
そんな関西と関東でのお雑煮の違いと特徴をそれぞれまとめてみました。
関西のお雑煮の主な特徴
関西のお雑煮は前述の説明やご紹介したレシピの通り、丸餅を使った白味噌仕立てであることが主な特徴になります。
丸餅を使うのは「円満」の意味が込められているためです。
具材は白味噌に合うものが使われているとされていますが、里芋に関しては別の意味があります。
お雑煮の文化が庶民に広まった当初は、米が高級品だったためお餅が高くて買えず、その代わりに里芋を使っていたのが由来とされています。
昆布のみで出汁を取るのは、白味噌が出汁や具材の味の影響を受けやすいためです。
この他の特徴としてはお餅を焼かずに煮て食べることも挙げられます。
関東のお雑煮の主な特徴
関東のお雑煮の主な特徴は、角餅を使った醤油仕立てのすまし煮であることになります。
具材も醤油仕立ての味付けに合うものが使われているようです。
また、関西の丸餅とは違い角餅を焼いて使うのも特徴と言えます。
関西と関東で使うお餅が違うのは、関東地方が武家中心の地方だったことが理由と考えられます。
関東のお雑煮に使われている角餅は「切り餅」とも呼び、のし餅を切ったものです。
この「のし餅」に敵を「のす」という意味を掛けて使われるようになったのが由来だそうです。
この他には、江戸が人口過多だったため、餅を大量生産するにはいちいち丸めるのは非効率であったことから、江戸を中心とした関東ではのし餅を切るだけの切り餅=角餅が使われるようになったとも言われています。
また、味付けに味噌が使われないのは、失敗して面目をつぶすという意味の「味噌をつける」という言葉を連想させるとして、武家では敬遠されていたことが理由のようです。
関西のお雑煮に関するよくある質問まとめ
関西地方のお雑煮には、どのような具材が使われますか?
関西地方のお雑煮では、具材として白味噌や鶏肉、大根、人参、そして焼いた餅が一般的です。
特に白味噌を使った甘めの味付けが特徴で、これが関西風お雑煮の大きな特徴となっています。
関西のお雑煮と関東のお雑煮の違いは何ですか?
最も大きな違いは味付けにあります。関西では白味噌ベースで甘めに仕上げるのに対し、関東では醤油ベースで少し塩辛い味わいが特徴です。
また、関東では焼いた餅ではなく、煮込んだ餅を使うことが一般的です。
なぜ関西地方では白味噌を使うのでしょうか?
関西地方は昔から白味噌の生産が盛んで、その文化がお雑煮にも反映されています。
白味噌は独特の甘みとまろやかな味わいがあり、これが関西のお雑煮に深い風味を与えているのです。
関西のお雑煮を作る際のポイントはありますか?
重要なのは、白味噌を使う際には、他の具材と調和を考えて慎重に量を加減することです。
また、餅はしっかりと焼き目をつけることで、香ばしさが加わり、お雑煮の風味を高めます。
お雑煮はいつ食べるものですか?
お雑煮は、元日を中心としたお正月の期間に食べられる伝統的な料理です。
新年の幸運を願い、家族みんなで食べることが多いですが、地域によってはお正月以外の時期にも楽しまれています。
関西のお雑煮に使われる白味噌はどんな種類が適していますか?
関西のお雑煮には、比較的甘みが強くてクリーミーな京都白味噌や兵庫の白味噌が適しています。
これらの白味噌は、お雑煮に豊かな味わいとまろやかさを与えるため、選ぶ際は甘みの強さや風味に注意してください。
関西のお雑煮を作る際、注意すべき調理のポイントは?
関西のお雑煮では、白味噌を入れ過ぎると味が濃くなりすぎるので注意が必要です。
また、具材は煮崩れないように優しく調理し、餅は焼いてから加えることで、適度な食感と香ばしさを出すことがポイントです。
関西地方以外でお雑煮を楽しむ際、代替材料を使う場合のアドバイスはありますか?
関西風の白味噌が手に入らない場合は、他の甘めの味噌で代用することが可能です。
ただし、本来の風味とは異なる場合があるため、味噌の種類によっては少量の砂糖やみりんで調整すると良いでしょう。
関西のお雑煮に合うおすすめのお酒はありますか?
関西のお雑煮には、味わい深い日本酒がよく合います。
特に、京都や兵庫産の日本酒は、お雑煮の甘みとのバランスが取れており、一層の味わいを楽しむことができます。
お雑煮の由来や歴史について教えてください。
お雑煮は、日本の伝統的な新年の祝いの料理であり、元々は神々に供えるためのものでした。
時代と共に、一般の家庭でも食されるようになり、地域によって異なる独自のスタイルが発展しました。
関西では、白味噌を使用するスタイルが根付いています。
まとめ
関西のお雑煮のレシピは具材や味付けが共通していますが、作り方にちょっとした違いが見られるのが面白いですね。
関東と関西で違いが出たのは、関東が武家中心の政権だったことに対し関西は公家中心の政権だったことを考えると何となく頷けます。
地方によるお雑煮の違いは関東と関西だけではないので、気になる方は是非調べてみてください。



コメント