鏡開きと言えばお正月にやる定番の風習ですが、そのやり方には決まりがあります。
鏡開きをする際に使うのは木づちかもしくは金づちなどの道具です。
包丁などの刃物は使用しません。
お正月の間に飾っておいた鏡餅は固くなっているからという理由もありますが、別の理由もあります。
今回の記事では鏡開きのやり方の手順について解説します。
また、最近よく見られる真空パックに入っている鏡餅での鏡開きのやり方についても説明したいと思います。
鏡開きの正しいやり方

鏡開きのやり方について説明します。まずは用意する物からご紹介します。
・木づち、もしくは金づち
・水に濡らして固く絞った布巾
次が鏡開きの手順です。
・年神様に感謝の気持ちを捧げながら鏡餅を下げる。
・硬く絞った布巾で鏡餅に付いたホコリや汚れを拭き取る。
・木づち、もしくは金づちなどで鏡餅を少しずつ叩きながらヒビを入れていき、最後に勢いよく叩いて鏡餅を割る。
以上が鏡開きのやり方になります。
この手順だと「開く」というよりは「割る」といった印象を受けますが、「割る」という言葉は縁起が悪いので使われません。
なので、縁起のいい末広がりを意味する「開く」という言葉を使い、鏡開きと呼ばれているそうです。
鏡開きをしたお餅はお雑煮やお汁粉などにして食べます。
鏡開きでやってはいけないこと

鏡開きでやってはいけないことは鏡餅を包丁などの刃物で切ることです。
「切る」という行為は縁起が悪いということもそうですが、これは鏡餅の起源とされる昔の武家で行われていた風習も関係しています。
その昔、武家ではお正月に男子は鎧や兜にお供えした具足餅、女性は鏡台にお供えした鏡餅を鏡開きの日に食べるという風習がありました。
その際に「餅を切るのは切腹を連想させる」ということで縁起が悪いとされ、具足餅や鏡餅には包丁などの刃物を入れなかったそうです。
もう一つは鏡餅が持つ意味に由来します。
鏡餅は年神様へのお供え物であるのと同時に、お正月の間は年神様が宿る依り代とされています。
そんな鏡餅を包丁などの刃物で切るのは「年神様に刃物を向ける」こととみなされていたため、鏡開きで刃物を使うのはやってはいけないこととされています。
鏡開きはいつやるの?

鏡開きは松の内が終わった後の1月11日に行われます。
松の内とは松飾りを飾っておく期間のことで1月1日から1月7日、もしくは1月15日がその松の内の期間となります。
鏡開きの日取りは関東と関西の地方によって異なり、関東は1月11日、関西では1月15日か1月20日に行われています。
また、関西でも京都と一部の近隣地域では1月4日が鏡開きの日とされています。
関東も江戸時代ごろまでは1月20日を鏡開きの日としていたのですが、三代目将軍徳川家光が4月20日に亡くなったことで、幕府が月命日に鏡開きをすることを避けるために鏡開きの日を1月20日から1月11日に変更したことが理由です。
硬いお餅を柔らかくする方法

鏡餅は鏡開きをする時にはカチカチに固くなっていることがほとんどです。
木づちや金づちなどで叩いて割るのはそのためでもありますが、木づちや金づちなどで叩いても割れないということもあります。
これは鏡餅の乾燥が中途半端な時に起こるようです。
そのような場合はどうするのかというと、鏡餅を水に浸けておくというのが最適な対処法のようです。
時間の目安はお餅の大きさによって変動し、手のひらサイズのものであれば4時間から5時間、大きめのものなら半日ほど水に浸けておけば大丈夫です。
それでも割れない場合は電子レンジで加熱するという方法があります。
電子レンジの場合は柔らかくなるまで加熱し、火傷しないように注意ながら手で千切ってしまってもOKなようです。
その場合は上の項で説明したように包丁などの刃物で切るのはNGです。
鏡餅が真空パックに入っている時の開け方
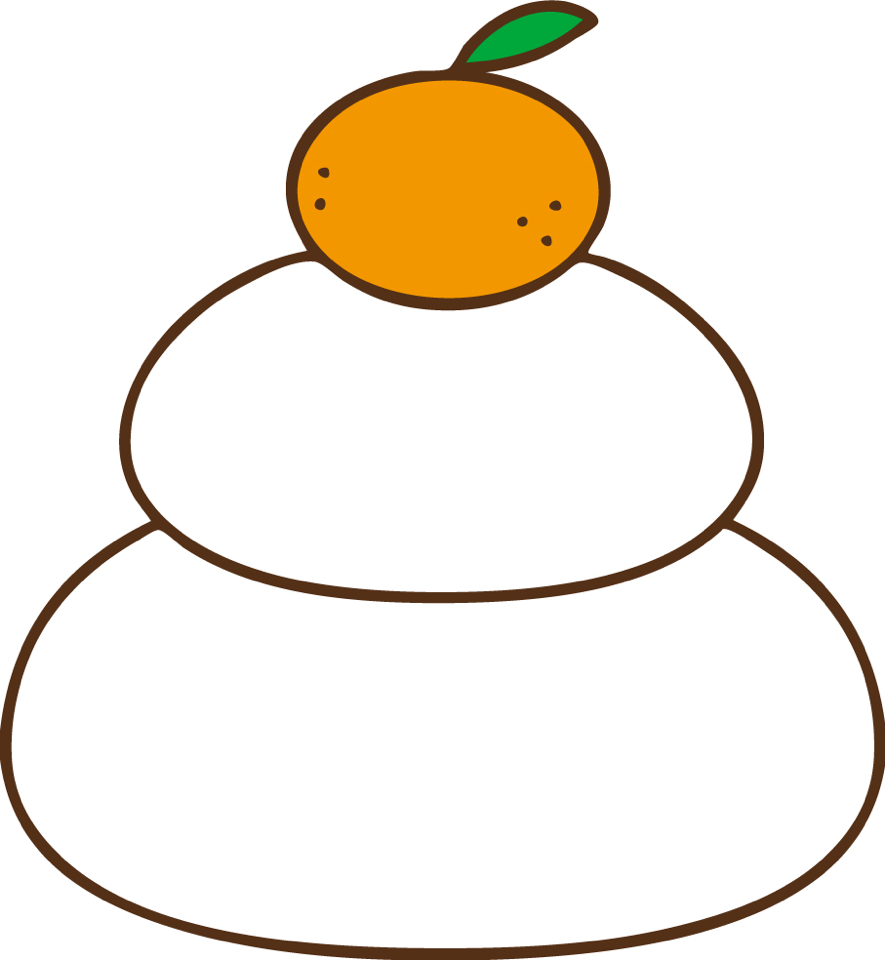
最近では鏡餅の形をした真空パックの中に切り餅や丸餅が入っているものが売られていますよね。
ほとんどの人は本物の鏡餅よりもこちらの方を飾っているという人の方が多いように思われます。
このタイプの鏡餅は木づちや金づちで叩いて割る必要はありません。
ハサミなどの刃物は使わずに真空パックを開けて中の切り餅か丸餅を取り出すだけでOKです。
切り餅や丸餅が袋に入って小分けになっていればいいのですが、お餅が丸ごと入れられている場合は少々手間がかかります。
お餅がパックの中に詰まってしまい取り出せないということが考えられるからです。
そのような場合はお餅をパックごとお湯で茹でるという対処法で解決できます。
鏡開きに関するよくある質問まとめ
鏡開きとはどのような行事ですか?
鏡開きは、正月に神棚や仏壇に供えられた鏡餅を取り下げ、開く儀式です。
この行事は、新年を迎えてから一定期間が経過した後に行われ、通常は1月11日に行われることが多いです。
鏡開きでは、鏡餅を割って、その後にそれを調理し、家族で食べることで、新年の祝福を分かち合います。
鏡開きの際の正しい鏡餅の割り方は何ですか?
鏡開きの際の鏡餅の割り方には、特別な方法があります。
まず、鏡餅を割る際には、包丁やハンマーは使わず、手や木槌などで優しく割ることが一般的です。
これは、鏡餅を切ることが縁を切ることにつながると考えられているためです。
また、割った鏡餅は通常、お汁粉やお雑煮などにして食べられます。
鏡開きはどこで行われるのですか?
鏡開きは、主に家庭や地域の集会、そして寺院や神社で行われます。
家庭では、正月に神棚や仏壇に供えた鏡餅を家族が一緒に割り、その後で食べます。
地域の集会では、地域社会の人々が集まって大きな鏡餅を共同で割り、神社や寺院では、訪れる人々と共に鏡開きが行われることがあります。
鏡開きの意味や由来は何ですか?
鏡開きの意味や由来は、新年の祝福を分かち合い、その年の繁栄を祈ることにあります。
鏡餅は、神様への供物として、新年に神棚や仏壇に供えられます。
鏡開きで鏡餅を割ることは、神様との絆を深め、家族や地域社会の繁栄を願う意味が込められています。
鏡開きに関連する風習や儀式はありますか?
鏡開きに関連する風習や儀式としては、鏡餅を供える際の儀式や、鏡餅を割る方法などがあります。
また、鏡餅を食べる際には、一緒に食べる食材や料理にも特別な意味が込められることがあります。
例えば、鏡餅を使ったお汁粉は、甘い味が家族の和を象徴するとされる場合があります。
これらの風習や儀式は、家族の絆や地域社会の和を大切にする日本の文化を反映しています。
鏡開きで割った鏡餅を食べる際の伝統的なレシピはありますか?
鏡開きで割った鏡餅を食べる際の伝統的なレシピには、お雑煮やおしるこ(甘い赤い豆のスープ)があります。
お雑煮は、地域によって異なる具材を使った日本の伝統的なスープで、鏡餅を入れて食べます。
また、おしるこに鏡餅を入れて甘く煮たものも人気です。
これらの料理は、鏡餅を美味しくお召し上がりいただく伝統的な方法として広く親しまれています。
鏡開きの際に注意すべきマナーやエチケットはありますか?
鏡開きの際のマナーとしては、まず鏡餅を割る際に神聖なものとして扱うことが重要です。
鏡餅を粗雑に扱ったり、不適切な道具で割ったりすることは避けるべきです。
また、割った鏡餅を食べる際には、それを共同で食すことで家族や仲間との絆を大切にする意識を持つことが望ましいです。
食事は、感謝の気持ちを込めていただくことが一般的なエチケットとされています。
鏡開きはどのような場所で行われるのが一般的ですか?
鏡開きは、一般的には家庭、地域のコミュニティ、神社、寺院などで行われます。
家庭では、家族が集まり、共に鏡餅を分かち合います。
地域の集会では、地域の人々が集まって鏡開きを行い、神社や寺院では、訪れる参拝者と共に鏡開きが行われることがあります。
これらの場所では、それぞれの伝統や習慣に従い、鏡開きが祝われます。
鏡開きの際、子供たちに伝えるべき教訓やメッセージは何ですか?
鏡開きの際、子供たちに伝えるべき教訓やメッセージには、感謝の心、家族や地域社会との絆の大切さ、新年の祝福を分かち合うことの意味が含まれます。
子供たちには、鏡開きの儀式が持つ文化的な意義や、それを通じて家族や友人との絆を深める機会であることを教えることが大切です。
また、新年の祝福を共に祝い、一年の繁栄を願うという伝統の意味を伝えることも重要です。
近年の鏡開きのトレンドや変化にはどのようなものがありますか?
近年の鏡開きのトレンドや変化としては、小規模な家庭や一人暮らし向けの小さな鏡餅を使うケースが増えています。
また、健康や多様性を意識した鏡餅の代替品、例えば砂糖を控えたものやアレルギー対応のものも見られます。
一方で、SNSを通じて鏡開きの様子を共有することが一般的になり、オンライン上で鏡開きの儀式を楽しむ人々も増えています。
伝統的な鏡開きの形式を守りつつ、現代の生活スタイルや価値観に合わせたアレンジが加えられている傾向があります。
まとめ
こうして見ると、場合によっては手間がかかってしまう印象を受けますね。
普通の鏡餅よりもてまがかからなさそうな真空パックの物でさえ、中にお餅が詰まってしまう場合があるというのも厄介です。
しかし、きっとそういったことも鏡開きの醍醐味のようなものなので、煩わしさを感じるよりも楽しむ気持ちを持ちたく思います。



コメント