今回はお食い初めを仏滅にすると縁起が悪いのか、六曜との関係はどうなっているのかを解説します。
お食い初めは別名『箸揃え』『箸初め』『百日祝い』などが存在しており、お食い初めを聞いたことがないという方でもそちらの名前で聞いたことはあるかもしれません。
名前が違うだけでやることは一緒なので、今回はこのようにいろんな呼び方があるお食い初めと仏滅を含めた六曜の関係性を調べつつ、お食い初めの情報もいろいろとまとめていきましょう。
お食い初めを仏滅にすると縁起が悪い?

仏滅は『勝負なしの日』や『仏も滅びる日』という意味があり、六曜の中で最悪の日と考えられています。
そして、仏滅は基本的に万事に凶で、1日中凶とされています。
特に、祭事や祝事との相性が悪いと解説されることが多いです。
そのことからも、基本的には他の六曜と比べて考えれば相性がいいとは言えません。
むしろ最悪の分類に入るでしょう。
仏滅にお食い初めをするときの注意点

仏滅にお食い初めをする際の特別な注意点はありません。
六曜的に仏滅は終日凶なので、気になって仕方が無いという人は別の日にするしかないでしょう。
ただし、お食い初めは赤ちゃんの生後100日頃に行われる大切な儀式であり、一生に一度しかない特別なイベントなので、仏滅だからといって日程をずらすことは基本的にありません。
日程調整や準備においては、この貴重なイベントに集中し、大切な思い出作りに専念したほうがいいでしょう。
お食い初めと六曜との関係は?

お食い初めは、赤ちゃんが生後100日頃に行う、健やかな成長を願う行事で、平安時代ごろから日本国内で行われていた行事となります。
一方、六曜は古代中国から伝来した暦で、吉凶を占うためのものです。
そのため、お食い初めと六曜は本来関係がありません。
六曜は江戸時代以降に広まりましたが、お食い初めは平安時代から存在していることを考慮すると、六曜とは異なる歴史を歩んでいることがわかります。
基本的にお食い初めの日取りを選ぶ際のポイントは、赤ちゃんの体調、家族や親族の都合、季節や天候、お店の予約状況などです。
六曜を気にする場合は、大安がおすすめですが、無理に大安に合わせる必要はありません。
お食い初めは赤ちゃんにとって初めての節目であり、大切な行事です。
六曜にとらわれず、ご家族にとって最適な日を選んでお祝いしましょう。
ただし、このお食い初めで招く親族の中に六曜を信じている方がいる場合は、六曜を無視することで揉め事に発展する可能性があるので、事前にそのような人がいるかどうかを調べることをお勧めします。
お食い初めをする理由は?

お食い初めは、赤ちゃんが生後100日を迎えた時に行われる儀式です。
この行事には、赤ちゃんの健やかな成長を願う深い意味が込められています
お食い初め(百日祝い)の意味
お食い初めには、大きく分けて二つの意味があります。
①一生涯、食べ物に困らないように願う
赤ちゃんに食事を模した行為をさせ、将来も栄養に恵まれるようにとの願いを込めます。
②離乳食の始まりを祝う
母乳だけでなく、固形物を口にできるようになったことを祝福します。
また、使用される食材とその意味は以下の通りです。
お食い初めの由来
この風習の起源は平安時代にさかのぼります。
当時は生後50日を”五十日”と呼び、それを祝う習わしがありました。
その後、お餅の儀式が加わり、江戸時代に近代的な形に定着しました。
世界各国で似たような儀式や行事があり、お隣中国でも中国由来という声も一部あります。
お食い初めには、たくさんの願いが込められた大切な行事なのです。
家族の愛情と赤ちゃんの健やかな成長への願いが、この儀式から伝わってきます。
お食い初めの日取りの決め方は?

お食い初めは、赤ちゃんが生後100日を迎えた際に行われる大切な行事です。
健やかな成長を願う家族の思いが込められているため、日取りの決め方には気をつける必要があります。
①赤ちゃんの状態を最優先
・首がすわって、離乳食を始められる体調であること
・生活リズムを崩さないよう、落ち着いた時間帯が望ましい
②家族の都合を考慮
・両家の祖父母を含め、多くの親族が集まれる日時
・平日よりも週末の方が参加しやすい
③時間帯は昼間が一般的
・昼間は参加が容易で、夜はゆっくり過ごせる
・長寿を願う場合、夜の時間帯を選ぶケースも
④季節を意識
・夏は涼しい午前中、冬は日中の暖かい時間が適している
⑤天気次第でも対応
・雨天の場合は、室内でも行える会場を選定
⑥その他の事項
・六曜を気にする場合は、大安や友引の日が吉日
・会場の予約が必要な場合は、早めの予約を
赤ちゃんへの祝福の気持ちを大切にしながら、上記のポイントを考慮して、理想的な日取りを決めましょう。
家族みんなが集まれる良い機会となるはずです。
お食い初めまでに準備することは?

お食い初めを円滑に行うために、以下の3点の準備が必要となります。
①儀式の準備
・赤ちゃんに食べ物の形を口に含ませる儀式用の膳が必要
・伝統的には漆器が使われますが、離乳食器や普段使いの食器でも可
・料理は赤飯、鯛、煮物、吸い物、歯固めの石の5種類を基本に用意
②衣装の準備
・赤ちゃんの衣装に決まりはないが、和風の雰囲気作りに適した服装がおすすめ
・動きを妨げない着心地の良い服が大切
・無理な着付けは避ける
③記念撮影の準備
・お食い初めは大切な節目なので、記念写真の撮影が望ましい
・プロに依頼する場合は、生後100日前後が一般的
・信頼できる写真スタジオを選び、早めの予約と打ち合わせが肝心
適切な準備を整えることで、華やかで思い出に残るお食い初めが実現できるでしょう。
赤ちゃんの健やかな成長を願う、大切な一日を万全の体制で迎えられます。
個人的な意見ですが、赤飯、鯛、煮物、吸い物、歯固めの石といったものは今の赤ちゃんからすると正直好まない物ばかりに見えてしまうので、そこまでの量を用意する必要は感じないですね。
大量に作らないようにした方がいいと思います。
仏滅に関するよくある質問
仏滅とは何ですか?
仏滅(ぶつめつ)とは、六曜の一つで、「何事も慎むべき日」とされる日です。
仏滅は六曜の中で最も不吉とされており、結婚式や新しい事業の開始、契約などを避けるのが一般的です。
仏教の「仏」とは関係がなく、もともとは「物滅」と書かれていたものが変化したとされています。
この日は、控えめに過ごすことが良いとされ、重要な決定や大きな行動は避けるのが賢明です。
仏滅に結婚式を挙げるのは避けるべきですか?
一般的には、仏滅に結婚式を挙げるのは避けるべきとされています。
仏滅は六曜の中でも最も不吉とされる日であり、多くの人が結婚式や重要なイベントをこの日に行うことを避けます。
しかし、一方で仏滅は式場やホテルが空いていることが多く、費用も抑えられるというメリットがあります。
仏滅にこだわらないカップルや費用を重視する場合には、仏滅に結婚式を挙げることも選択肢の一つです。
仏滅に引っ越しをするのは良くないですか?
仏滅に引っ越しをすることも、一般的には避けるべきとされています。
仏滅は不吉な日とされるため、新しい生活のスタートを切る日としては適さないと考えられています。
ただし、引っ越しの日程が仏滅しか取れない場合や、あまり気にしない人もいます。
仏滅を気にしない場合は、自分の都合に合わせて引っ越しを行っても問題ありませんが、可能であれば仏滅以外の日を選ぶと良いでしょう。
仏滅に新しい仕事を始めるのは避けるべきですか?
仏滅に新しい仕事を始めることも、一般的には避けるべきとされています。
新しいスタートを切る日としては不吉とされるため、初出勤日や開業日としては避けるのが無難です。
しかし、現代では六曜を気にしない人も増えており、実際には仏滅に仕事を始めても大きな問題が起こるわけではありません。
気にしない場合は、自分のスケジュールに合わせて行動しても良いですが、周囲の意見や風習も考慮することが大切です。
仏滅に行動を控えるべき理由は何ですか?
仏滅に行動を控えるべき理由は、六曜の中で最も不吉な日とされるためです。
古くから、日本の風習では仏滅の日に重要な行事や新しいことを始めるのは避けるべきとされてきました。
これは、仏滅の日に始めたことがうまくいかないという迷信から来ています。
現代では、必ずしも仏滅を避ける必要はありませんが、伝統や風習を重んじる人々にとっては、仏滅の日に重要な決定や行動を避けることが大切とされています。
仏滅のお食い初めまとめ
以上、いかがでしたか。
今回はお食い初めと仏滅の関係性についてまとめつつ、六曜との関係性についても触れてきました。
お食い初めは中国由来という声もありますが、平安時代からあったとのことなのでたとえ中国から伝わった風習だったとしてもほぼほぼ日本オリジナルと言えるような文化になっていると思います。
しかし、現代日本ではかなり薄れてしまった風習でもあるので、実行するときはどういったやり方をするのかなどを調べておく必要があるでしょう。
そういった知識があるご年配の方々に聞いてみるというのもいいですよ。
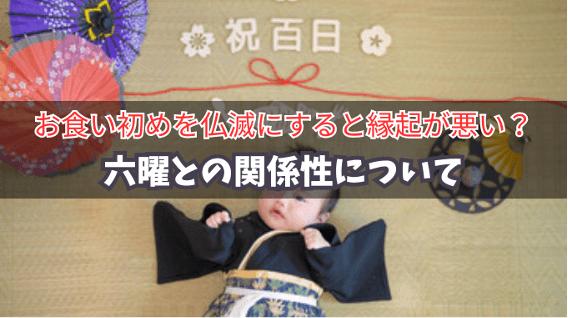
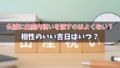
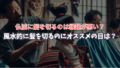
コメント